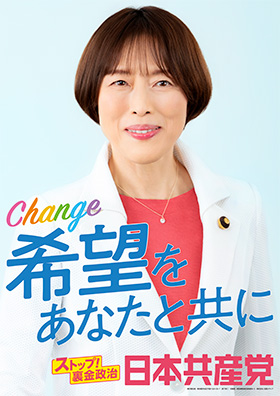安倍流〝地方分権〟 学童保育基準緩和は安全軽視 宮本岳氏が批判 衆院地方創生特
日本共産党の宮本岳志議員は15日の衆院地方創生特別委員会で、学童保育指導員の基準を緩和する動きを例に、安倍政権の〝地方分権改革〟の一環で導入された「提案募集方式」は、専門知見や安全・安心をないがしろにした規制緩和だと告発しました。
同方式は、地方公共団体等の提案をうけ、国が法改正などで実現を図るもの。これを用いて地方3団体が指導員の配置・資格基準の緩和を提案。昨年12月、「平成30年(18年)度中に結論を得る」と閣議決定され、早ければ来年度から緩和される危険があります。
宮本氏は、内閣府の部会で、安全・適切な環境を確保するため緩和に難色を示した厚労省を、部会構成員が激しく批判し緩和を迫っていると指摘。「構成員に学童保育や子どもの専門家はおらず、現場視察や指導員への聞き取りもしていない」として、社会保障審議会の議論など、子どもの命と安全に関わる専門知見を軽んじる内閣府の姿勢を批判しました。
梶山弘志地方創生相は「関係府省の審議会等での議論を排除する仕組みではない」と強弁。宮本氏は「それならば社保審の議論を尊重するべきだ。専門家のいない場で決めるという愚かなことは直ちにやめるべきだ」として、〝地方分権改革〟を盾に最低生活保障(ナショナルミニマム)を突き崩すことは許されないと主張しました。
( 赤旗2018/6/16)
動画 https://youtu.be/Gi5fudFlYMU
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
この第八次地方分権一括法案は、提案募集方式に基づいて義務づけ、枠づけの見直しを行うというものでありますけれども、この間の提案募集方式は、地方の創意を生かすというようなものではなく、それを錦の御旗に国が責任を持つべきナショナルミニマムを突き崩し、地方自治体を国策に誘導する手段に使われていると言わなければなりません。
その典型例が、三月十六日、当委員会で大臣と議論した学童保育指導員の配置基準や資格基準を従うべき基準から参酌基準に引き下げる基準緩和の検討であります。
三月にも申し上げましたけれども、就学児童に対する保育ニーズが高まり、学童保育が足りていないこと、学童保育の指導員が慢性的な人手不足であることは私も重々わかっております。しかし、その原因は、三月に大臣が答弁したような硬直的な基準に問題があるわけではありません。一番の問題は、労働条件と処遇の改善が進んでいないことであります。
内閣府に聞きますけれども、内閣府は、劣悪な学童保育指導員の低賃金、労働条件について掌握をしておりますか。
○大村政府参考人 お答えいたします。
処遇の状況について私どもが直接把握をしているということはございません。
ただ、私どもの議論の中で、厚労省と十分な連携を図って議論していきたいと思っております。
○宮本(岳)委員 直接つかんでもいない、それは厚生労働省に聞いてくれと。
前回、厚生労働省からは、平成二十八年度の調査結果を答弁してもらいました。指導員の約七割程度は非常勤職員やパート、アルバイトが占めていること、給与も年額二百七十万円にとどまっているということが明らかになりました。
そこで、内閣府に聞くんですけれども、この従うべき基準の廃止や参酌化を要求している自治体はどれほど学童保育指導員の処遇改善の取組をしてきたか、つかんでおりますか。
○大村政府参考人 お答えいたします。
私ども、先ほど申しましたように、この点について直接把握しているわけではございません。厚労省の方で把握していただいておりますけれども、全国知事会ほか三団体の提案でございますけれども、また、それ以外にも共同提案団体などもございます。そういう中で、処遇改善を実施している団体が一定程度あるというふうに聞いております。
○宮本(岳)委員 まともにつかんでいないんですよ。
処遇改善の努力を尽くした上で、それでも指導員が集まらない、これは、従うべき基準が厳し過ぎるというのならともかく、どれだけ処遇改善の努力をしたか、それもつかまずにやろうとしている。それでは、処遇が悪いのか、基準が悪いのか、全くわからないと言わなければなりません。
では、厚生労働省に聞きたいと思います。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に係る従うべき基準の廃止又は参酌化を提案する市町村における放課後児童支援員等処遇改善等事業及び放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施状況を、厚労省、答えていただけますか。
○成田政府参考人 参酌化に係る御提案は全国知事会等から出されたものであり、支障事例を抱えている自治体の全てを把握しておりませんが、当該提案に係る共同提案団体として具体的に把握している五件、七市のうち、平成二十九年度において、放課後児童支援員等処遇改善等事業を実施している自治体は二市、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施している自治体は四市であると承知しております。
○宮本(岳)委員 厚労省から提出された資料を皆さんにお配りをしておきました。資料一を見ていただきたい。提案している市町村、七市町村のうち、二つある処遇改善事業を両方ともやっているのは茨城県ひたちなか市のみ。静岡県伊豆の国市や山口県防府市などは、処遇改善事業を何一つせず、基準の廃止や参酌化だけを求めております。
自治体の提案が学童保育指導員の処遇改善の努力をきちんと尽くした上でのものなのか、それとも、処遇改善はそっちのけで基準崩しだけを求めているのか、それを判断するにも、今まさに自治体の状況をつかんでいたのは厚生労働省だったと言わなければなりません。
にもかかわらず、この従うべき基準の参酌化という子供の命、安全にかかわる大事な問題を厚労省の社会保障審議会から無理やり地方分権の場に取り上げるという、こういうむごい閣議決定をやったわけでありますけれども、なぜやったんですか、大臣。
○梶山国務大臣 放課後児童クラブの置かれている状況は、都市部と地方部など、地域の実情に応じて大きく異なるものであり、それらの異なる状況に対し全国一律の基準が適用されていることで、クラブの円滑な運営に支障が生じていることが課題と考えております。
学童保育の安全性の確保等、一定の質の担保は極めて重要であります。このことも含めて、地域の実情を踏まえた柔軟な対応により、今後とも放課後児童健全育成事業が地域のニーズに応えて円滑に行えるように検討してまいりたいと思いますし、地域にもしっかりとした努力をしていただきたいと思っております。
○宮本(岳)委員 答えになっていないんですよ。基準が障害だということが検証されていないということを私は言っているわけですね。
私は、この間の地方分権改革有識者会議提案募集検討専門部会における議論を一通り読ませていただきました。
まず、昨年九月一日の第六十回専門部会では、地方三団体から意見を聞いております。これを受けて、十月十六日の第六十四回専門部会には、厚生労働省の成田審議官が担当課長や室長とともに呼ばれております。
冒頭、高橋部会長は、原則論として国が基準を示す必要があることに異論はないが、従うべき基準とするかどうかが問題であると切り出し、地方三団体から、放課後児童クラブ人員基準について従うべき基準となっているため、事業展開ができないとの声が出されている、標準や参酌すべき基準とすることもできるが、従うべき基準にしなければならない理由について御説明いただきたいと成田審議官に迫りました。
これに対して、成田さんは、国の制度として放課後児童クラブを実施している以上、子供の安全や適切な環境確保のために必要最低限の基準が必要である、保育や養護等についても従事者の資格及び員数については従うべき基準とされていると、当然の回答を行っております。
成田審議官、間違いないですね。
○成田政府参考人 昨年十月の地方分権改革有識者会議におきましては、放課後児童健全育成事業の従うべき基準の参酌化に係る御提案に対し、厚生労働省からは、人口が少ないなどの理由により放課後児童支援員の確保が困難であるなど、放課後児童健全育成事業を行う自治体からの支障事例について、その解決ができるよう努めること、一方で、児童の安全確保や放課後児童クラブの質の確保を図る上で従うべき基準を設け、放課後児童支援員の配置や研修受講を全国一律に求めることが必要であることなどを回答したところでございます。
○宮本(岳)委員 そう回答したわけですよね。ところが、これに対して矢のような批判が浴びせられております。
大橋構成員からは、地方三団体は従うべき基準とすることについて地方側に十分な説明がなかったと言っているとか、義務づけが許されるのは、第三次勧告により真に必要な場合に限られており、当事者に十分な説明がなされるのが筋だと言い、参酌すべき基準とすることを念頭に検討せよと迫りました。
伊藤構成員は、従うべき基準でなければ安全性や質が担保されないという考え方が分権の趣旨からは納得できない、ことし参酌化を求める提案として、運営上の不安が表面化していることを踏まえ御対応いただきたいと迫りました。
それでも成田審議官は、従うべき基準を設定した上で配置基準や認定資格研修の受講を全国一律に求めることは必要、その点について柔軟化することは困難と言いつつも、個別の案件には地域の実情を踏まえて対応する旨を答えております。
すると、勢一構成員は、地域の実情を踏まえた対応を行っていただくということだが、地域の実情を踏まえた要件を判断する主体は国でなければならないのか、分権の仕組みとしては、地域の実情に合わせて地方公共団体が遵守しなければならない基準を判断すべきだと主張し、徹底的に厚労省を袋だたきにしていると私は受けとめました。
成田審議官、ここであなたは説き伏せられてしまったんですか。
○成田政府参考人 昨年十月の会議におきましては、厚生労働省として申し上げるべきことを申し上げた上で、最終的に年末の閣議決定になったというふうに考えております。
○宮本(岳)委員 この議事録を読む限り、成田審議官はよく頑張って踏みとどまっております。
ところが、昨年十二月二十六日、放課後児童クラブに関する従うべき基準の参酌化を地方分権の場において検討し、平成三十年度中に結論を得るなどという閣議決定が行われると、完全に流れが変わるんですね。
ことし二月十九日に開催された第七十回専門部会では、ついに吉田子ども家庭局長が、従うべき基準の見直しについては、幾つかのテーマがあるが、平成三十年八月を目途に具体的な検討を進めてまいりたいと折れました。
大橋構成員が、今から結論の話をすべきではないと思うが、現行の児童福祉法第三十四条八の二の第二項において、放課後児童クラブに従事する者と員数については従うべき基準であることが明記されている、当該条文の改正等も視野に入れて今後の検討を進めていただけるという理解でよいかと聞きますと、吉田局長は、厚生労働省として誠実に対応させていただきたいと言い、高橋部会長は、最後に、現在、厚生労働省で新たな放課後育成事業のあり方について検討していると思うが、従うべき基準の廃止、縮減の方向で今後の制度設計についても御検討いただきたい。部会長がそう結んでおります。
厚労省、これは完全に屈服したということですか。
○成田政府参考人 厚生労働省といたしましては、閣議決定にございますように、地方分権の議論の場において検討し、平成三十年度中に結論を得ることとしているというふうに理解しております。
○宮本(岳)委員 このやり方は本当にひど過ぎると言わなければなりません。
私は、この議事概要というものを読んでいて、かつてこれとうり二つの議事録を読んだことを思い出しました。今治市に新たな獣医学部の設置を認めた国家戦略特区諮問会議の国家戦略特区ワーキンググループの議事録であります。
平成二十七年六月五日に今治市と愛媛県から提案ヒアリングというものを受けますと、三日後の六月八日には関係省庁ヒアリングということで、民間委員らが獣医学部新設を認めない文部科学省を袋だたきにいたしました。あの構図にそっくりだと言わなければなりません。
大臣、これは結局、地方分権改革なる看板を掲げて、専門性を有する所管官庁が子供の安全や保育の質の面からナショナルミニマムをないがしろにすることはできないというものを、とにかく形式批判で袋だたきにして規制緩和を迫る、まさにあなた方安倍内閣のお決まりのやり方ではないんですか、大臣。
○梶山国務大臣 提案募集方式によって地方分権改革として地方から受けた提案につきましては、地方分権の議論の場において議論し、対応方針を決定することとしております。その際、提案を受けた関係府省は、対応を検討するに当たり、必要に応じて関係する審議会等の御意見を考慮して検討を行っており、内閣府として、関係府省の審議会等の議論を排除する、又は関与させないような仕組みをしていることは従来からないと思っております。
また、この放課後児童クラブの件に関しましては、地方三団体から参酌化を求める意見が繰り返し表明されたことを踏まえて、厚生労働省だけで判断するのではなく、地方分権の議論の場でしっかりと地方公共団体の意見を踏まえて検討することを確認的に明記をしたものであります。
地方三団体は、地方公共団体の声が無視されることを危惧しているところもございます。
○宮本(岳)委員 ならば、配付資料二を見ていただきたい。内閣府が私に提出した第六十四回提案募集検討専門部会、当時の構成員名簿であります。
内閣府にこれは聞きますけれども、この八人は全員が行政法や行政学が専攻の法学者ではありませんか。一人でも子供の専門家はおりますか。
○大村政府参考人 お答えいたします。
私どもの有識者会議の議員は、行政法、行政学を通じて地方公共団体の行政全般について精通している皆様であるというふうに考えております。
○宮本(岳)委員 改めて確認をいたしました。全員が行政法、たったお一人行政学でありますけれども、学童保育や子供の保育についての専門家はただの一人もおられません。
内閣府に重ねて聞きますけれども、このメンバーが学童保育の現場を視察したり指導員の話を聞いたりということをやったことはありますか。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。
必要に応じて、先生方の視察、私ども、全国に向けて、提案に当たって視察等も企画しておりますので、そのときには参加していただくこともあります。
たまたま現在までの段階ではそういった放課後児童クラブに直接行っていただいているということはございませんが、ただ、先ほど大臣から申し上げましたとおり、関係府省との間できっちりとそこのところは議論を積み上げて丁寧な形でこの分権の議論をやっておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○宮本(岳)委員 だらだら言いわけしなくていいですよ。行っていないんじゃないか。
しかも、上から三人目、何度も出てくる高橋滋法政大学法学部教授は部会長でありますけれども、規制改革会議行政手続部会の部会長でもあるんです。
大臣、何で学童保育の現場を知らない行政法学者に子供の命や安全、発達にかかわる学童保育指導員の基準のことを決めさせるのか。決められるわけがないではありませんか、大臣。
○梶山国務大臣 先ほども申し上げましたように、内閣府として、関係府省の審議会等の議論を排除するような仕組みにはしておりません。
そして、これらについても安全性の確保は当たり前のことでありまして、それらも含めて地方自治の範囲ということで考えております。
○宮本(岳)委員 関係府省の議論を排除するものではないというふうに何度もお答えになるので、では確認しますけれども、社会保障審議会の専門部会は、ここでもきちっと議論していいんですね、大臣。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。
私ども、厚労省と十分に連携して検討していくということが前提になっております。
そして、地方分権の場で議論するということを書いたのは、これは確認的に書いたものでございまして、そもそも地方分権の提案については、もともとこの有識者会議の議論の場で議論していく、これは全般にそうでございます。
ただ、地方団体から、いろいろな経緯があり、強い声があったので、地方分権の議論の場ということを確認的に書いたものでございますので、ある意味、一般的にこういう形をとっておるということでございます。
そういう中で、厚労省の審議会で議論していることは私どもも十分に存じております。そういう点の御審議を踏まえて厚労省では私どもの方にいろいろな形でお話をいただくということになっておりますので、当然に、全体的なことについて総合的に、先ほどいただいた処遇の件も、それから従うべき基準の件もトータルで、私ども、そもそも、これはあくまで、放課後児童クラブのサービスを十分に供給してお子さんたちの待機児童を解消したい、こういう観点からやっておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○宮本(岳)委員 いや、子供のためになるかならないか、命と安全にかかわるから議論しているんですよ。そこまでおっしゃるのであれば、社会保障審議会児童部会の専門委員会の議論をしっかりと尊重しなければならないと思います。
閣議決定で、従うべき基準の検討を社会保障審議会児童部会の専門委員会から取り上げて、行政法学者ばかりの地方分権の場で決めるというような愚かなことは直ちにやめることを求めて、私の質問を終わります。