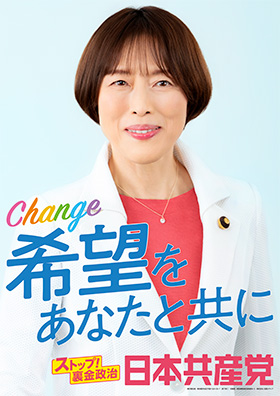平成二十二年四月九日(金曜日)
午前九時三分開議
出席委員
委員長 田中眞紀子君
理事 奥村 展三君 理事 首藤 信彦君
理事 松崎 哲久君 理事 本村賢太郎君
理事 笠 浩史君 理事 坂本 哲志君
理事 馳 浩君 理事 富田 茂之君
石井登志郎君 石田 勝之君
石田 芳弘君 江端 貴子君
川口 浩君 城井 崇君
熊谷 貞俊君 後藤 斎君
佐藤ゆうこ君 瑞慶覧長敏君
高井 美穂君 高野 守君
中川 正春君 平山 泰朗君
牧 義夫君 松本 龍君
湯原 俊二君 横光 克彦君
横山 北斗君 吉田 統彦君
あべ 俊子君 遠藤 利明君
北村 茂男君 塩谷 立君
下村 博文君 菅原 一秀君
永岡 桂子君 古屋 圭司君
松野 博一君 池坊 保子君
宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 川端 達夫君
文部科学副大臣 中川 正春君
文部科学副大臣 鈴木 寛君
文部科学大臣政務官 後藤 斎君
文部科学大臣政務官 高井 美穂君
厚生労働大臣政務官 山井 和則君
経済産業大臣政務官 高橋 千秋君
環境大臣政務官 大谷 信盛君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局長) 泉 紳一郎君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 藤木 完治君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 平野 良雄君
文部科学委員会専門員 芝 新一君
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
菅原 一秀君 あべ 俊子君
同日
辞任 補欠選任
あべ 俊子君 菅原 一秀君
―――――――――――――
四月八日
すべての学校図書館へ、専任・専門・正規の学校司書の配置を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六四四号)
同(笠井亮君紹介)(第六四五号)
同(穀田恵二君紹介)(第六四六号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第六四七号)
同(志位和夫君紹介)(第六四八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六四九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第六五〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第六五一号)
同(吉井英勝君紹介)(第六五二号)
教育格差をなくし、すべての子供たちに行き届いた教育に関する請願(志位和夫君紹介)(第六五三号)
同(稲津久君紹介)(第七六八号)
同(宮島大典君紹介)(第七六九号)
教育格差をなくし、行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(梶原康弘君紹介)(第六六五号)
私立幼稚園教育の充実と発展に関する請願(石田芳弘君紹介)(第七〇六号)
教育格差をなくし行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(野田毅君紹介)(第七三七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
――――◇―――――
○田中委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。宮本岳志君。
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。
本法案にはさまざまな改正点がありますけれども、主要な改正は、クリアランス制度の導入であります。
クリアランスの基準とされる〇・〇一ミリシーベルト以下のものを放射性汚染物から除外することは、一定の合理性もあり、異論はございません。
ただ、放射線、原子力に対する国民の不信、不安が広く存在しておりますし、そもそも放射線防護の観点からは、できるだけ人体に放射線を受けないことが望ましいことは明瞭であります。
問題は、クリアランス制度を実施する場合、国民の安全の観点から、放射能濃度の高い放射性汚染物が産業廃棄物として処分、再利用されるようなことがないように制度的に担保されているのかどうかが問われると言わなければなりません。放射能濃度が高い汚染物が産業廃棄物として処分されることは、国民の安全を確保する点からも、万が一にもあってはならない。これはもう当然のことであります。
そこで、本法案で導入されるクリアランス制度は、放射能濃度の測定と評価方法について国の許可を得れば、放射性同位元素を扱うあらゆる事業者がクリアランスの実施主体となることができる、そういう仕組みになっているわけですね。
そこでまず最初にお伺いいたしますけれども、その事業者の放射性同位元素の管理の実態がどうなっているか、これを確認したいんです。
昨年、二〇〇九年一年間で、管理下にない放射性同位元素の発見、放射性同位元素の所在不明となった事例、これはそれぞれ何件あるか、お答えいただけますか。
○泉政府参考人 お尋ねの、二〇〇九年の一年間でまず所在不明になった件数でございますけれども、三件でございます。
それから、管理下にない放射性同位元素の発見件数でございますけれども、これにつきましては、二〇〇九年の十月一日付で、一年を期限としまして、使用事業者等に対しまして、管理下にない放射性同位元素の一斉点検とその結果の報告を依頼したところでございまして、これまでの報告については現在取りまとめ中でございますけれども、二〇〇九年の一月からこの一斉点検の依頼をする前までの二〇〇九年の九月末までに発見されました管理下にない放射性同位元素の発見件数は、四件ということになっております。
○宮本委員 現に今でも、所在不明となった事例や、あるいは、管理下にない放射性同位元素が発見されているという実態があるんですね。
先ほど御答弁にあったように、文部科学省は昨年十月に、放射性同位元素を扱う事業者に対して、「管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点検の実施及び報告依頼について」という文書を出しておられます。この文書の趣旨、そして、この報告を求めている目的は何ですか。
○泉政府参考人 この一斉点検の趣旨でございますけれども、これは、管理区域の外に置かれていた放射性同位元素の発見等があるという事例が相次いだことから、許可届け出の使用者及び許可の廃棄事業者に対しまして、放射性同位元素等が適切に保管されているかどうかについて、管理区域の外の居室あるいは実験室などで、長年こういった形で放置されている放射性同位元素がないかどうかを点検してもらうというのが趣旨でございます。
○宮本委員 ここにその現物がありますけれども、前書きにこうありますね。「しかしながら、今なお管理されていない放射性同位元素等の発見が散見され、現在の管理が適切であったとしても、過去に購入された線源が管理されないまま存在している状況が報告されております。その原因は、平成十七年に実施していただいた管理下にない放射性同位元素等の調査に不十分な点があったのではないかと考えております。」したがって、「管理区域のみならず、管理区域外についても、」「長年放置されている放射性同位元素等がないか、今一度、別添に示す手順により一斉点検をしていただくようお願いします。」こういう文章ですよね。
それで、今なお、管理されていないそういう放射性同位元素が発見されている。また、二〇〇五年の調査は不十分だったということもこの通知ではっきりと認めておられます。しかもこの一斉点検、まだ現在進行中でありまして、ことしの九月末までにそれを取りまとめるという状況なんですね。すべての事業者が適切に管理しているのか、今の時点でその最終確認すらできていないのが現状だと思うんです。
この状態ですべての事業者がクリアランスができるような状況をつくり出すというのは、私は非常に不安がある、心配があると言わざるを得ないと思うんですけれども、これは大臣、どうお考えですか。
○川端国務大臣 御指摘のように、現在一斉点検を行っている、そして、管理下にない放射性同位元素の存在が年に何件かあったということは事実であります。過去に起こった。調べましたら、要するに、昔のものであったということで言えば、十七年ですか、やったときに見つからなかったという意味では、十分でなかったというのは間違いない事実であることはそのとおりだと思います。
ただ、そういう部分で、現在取りまとめ中でございますが、前回そういう不十分であったことを踏まえてしっかりやることで、一定の取りまとめをする中で適切な状況がつくれるというふうに思っておりますが、同時に、今回のクリアランスの部分は、管理下にあるクリアランス、要するに、もう使い終わったものをどう処理するかという趣旨のものでありまして、今までの管理で所在がわからなくなってしまったものがどうあるかということと、これを万全を期すというものと、それが不十分であるからクリアランスはやれないというのとはちょっと性格が違うというふうに私たちは思っております。
現在、規制の体系下にある同位元素を、もうくどくど申しませんが、法案の趣旨に従って測定、評価そして管理をしっかりやるという法体系の中で、この中にクリアランス対象外がまじるというふうなことを排除する仕組みで十分に安全性は保たれるというふうに思っております。管理下にないものがあるというものとは性格は異にするという対応をしているつもりでございます。
○宮本委員 十分に安全が担保されるかどうかということが、これから一つ論点になってくると思うんですね。
それで、想定されているクリアランスをお伺いしますと、放射性同位元素のうち、半減期の短いものに汚染されたものだけを一定期間保管して除外する、こういうふうにお聞きをいたしました。
しかし、今改めて文部科学省も報告を求めているように、どんな種類の放射性同位元素があるのか正確に把握できていない現状がある。調べてみたら実はこんなものがありましたよという事業者が現に存在しているにもかかわらず、厳格に半減期の短い放射性同位元素だけより分けて処分することができる、こう言われても、本当にそんなことができるのかと疑問に思うのは当然だと私は思うんですけれども、そういう疑問は当然じゃないでしょうか。
○川端国務大臣 これは当然、半減期の短いものを取り分けて保管することはできる。それで、半減期を過ぎて一定期間、これも、人間の暮らしでいう常識的な短い期間で半減期を経て放射線量が基準以下になるということが確認できれば、それはそういうこととしての処分ができますよということであって、クリアランスにするというときには全体を一緒に保管をして、クリアランス対象としての基準での測定、評価をして行うことを当然やっていいわけですから、半減期が短いものだけを取り分けてやるということをしてもいいという意味であって、必ずやりなさいという意味ではなく、そのものを含めた部分が全体としてクリアランスの対象として当然ながら入るわけですから、今御指摘のような想定外のものがということは、この半減期のものだけだということで測定をしてひっかかればそれでだめですから、そういう意味では、そのものだけという特定できるようなものがあれば、分けて保管をして除外をすることは可能であるということを言っているだけであると御理解をいただきたいと思います。
例えばPETなんかで、私も受けているんですが、RI化したブドウ糖を打ちますけれども、あれは本当に半減期が短いので、検診が終わって一日もたてば、多分、体の中で半減期が全部終わってしまうというものはそういう処置が当然できるということを想定しているんだと私なりに理解をしております。
○宮本委員 もちろん、だから冒頭申し上げたように、〇・〇一ミリシーベルト以下のものをクリアランスするというこのこと自身に、別に大した異論があるわけじゃないんですよ。ただ、現状が、本当にそういうものの中にそれを超えたものがまじらないかどうかということを一つ一つ検証する必要があると思うんですね。
何かありますか。では大臣。
○川端国務大臣 そういう意味で、仕組み的にはそういうふうに分けてやることはできるということでありますが、当面は、制度が安定して動くまでは、全部クリアランスの対象とするというふうに考えております。
○宮本委員 既に放射性廃棄物をめぐっては、これまでも問題となる事件、事例がたびたび起こってまいりました。
そこでまず、事実の報告を求めたいのですが、二〇〇六年六月に旧大阪府立産業技術総合研究所で起こった事例、二つ目に、二〇〇七年五月の大阪府立母子保健総合医療センター研究所での事例を、これは事実ですから、事務方で結構です、説明してください。
○泉政府参考人 お尋ねの事例の一番目でございますけれども、これは大阪府の旧大阪府立産業技術総合研究所の件でございます。
この研究所の跡地、これは平成八年に研究所が移転されておりますけれども、この跡地において放射能標識のついた金属容器が発見されたという連絡が大阪府から当時文部科学省にございまして、その連絡があった翌日に文部科学省が立入調査を行ったところ、その発見された容器というのは空であったところでございますけれども、容器それからこの容器が見つかった部屋の内部にわずかながら汚染が認められたということでございました。この汚染による放射線障害のおそれあるいは環境への影響はなかったということでございます。
それから二番目の件ですけれども、これは大阪府立母子保健総合医療センター研究所の件でございます。
これは、この研究所において使っていた微量の放射性同位元素を含む物品を誤って廃棄したという連絡がございました。それで、この物品は一般廃棄物として回収、焼却された可能性があるわけでございますけれども、含まれている放射性同位元素の数量はごく微量、これは炭素14で百キロベクレルということで、環境への影響はなかったということでございます。
○宮本委員 いずれも軽微だという話ですけれども、もちろん、それはそうであればこそ今日大事件になっていないわけであって、ただ、問題は、公的機関でさえ、現に、放射性廃棄物を放置していたり、誤って一般廃棄物として捨ててしまったという事例が起こっているわけですよ。この母子医療センターは一般ごみ箱に投入したとなっていますから、放射性廃棄物に当たるものをごみとして捨てた、そういう事故が現に起こっているわけですよ。
こんな状況でクリアランス制度を導入したら、それこそ、放射性汚染物から除外するというものを間違ってどんどん一般廃棄物としてあるいは産業廃棄物として、そういうところへ捨ててしまうという事態が起こり得るのではないかと私は思うんですけれども、これはその危険性はないと断言できますか。
○川端国務大臣 先ほどと同じようなことなんですけれども、いわゆる放射性同位元素を含む物質を管理するという点において、過去に、要するに管理されていないものが出てきたとかいう部分、あるいは、それを保管、保存するときに誤廃棄をしたということが起こったことは事実であります。それぞれに二度と起こらないような対策を含めてやっておりますが、それと、管理された状況で廃棄物が出たときに、それを保存し続けるか、厳格な基準と評価方法と管理、監視のもとにそれをクリアランスして処分する、保存処理じゃなくて、廃棄処分ができるように極めて低濃度のものを処理するという仕組みとは、性格は違うものだというふうに私は思っています。
こういうあってはいけないような誤廃棄や、あるいは所在不明のものが出てきたということをもって、クリアランスするのはいかがなものかというのとはちょっと性格の違う議論ではないかというふうに私としては思っておりますし、このクリアランスするに関しては、先ほど来の議論、法の仕組みも含めて評価・測定方法、それからその部分の認可、そして立入検査等々を含めてしっかりとした確保をするということ。
多分、委員は、どうしてもいいかげんなことをする人がいるではないかということなのかもしれませんが、現在、ただ単に保管をしていくということには保管する以外の法の網は一切かかっておりませんから誤廃棄も起こったのかもしれませんが、そういうのは、むしろ出口もしっかりするという意味でも、安全に対しては万全を期していく仕組みとして考えているところでございます。
○宮本委員 その厳格な管理、監視のもとにクリアランスがされるのであれば、そして、間違いなく〇・〇一ミリシーベルト以下であるということが本当に責任を持って確認できるのであれば、このクリアランスという制度に合理性がある、これは冒頭から申し上げているわけですよ。
しかし、現状の、核汚染物質の管理もそうですけれども、また、産業廃棄物の取り扱いということを見たときにも、実際にはそれがきちっと担保されない事態が起こっているのではないかということを申し上げているわけです。
それで、国がクリアランスの結果を確認するとおっしゃるわけですけれども、それでは、クリアランスされたものすべてを全量国が検査するんですか。事務方、いかがですか。
○泉政府参考人 この確認でございますけれども、国または登録の濃度確認機関が確認をするわけでございますが、事業者が、認可された方法で行ったクリアランス対象物の測定・評価結果の確認を行うわけでございます。この測定・評価結果が放射能濃度基準を超えていないかにつきましては、全記録を確認するということでございます。
それで、さらに現場において、事業者は全部はかっているわけですけれども、一部サンプリングを行いまして抜き取りを行って、実際にこれをはかりまして全記録の信頼性を確認するということといたしております。
○宮本委員 事業者は全部を確認する、当たり前であって、でないとクリアランスにならへんので、確認もせずにこれは大丈夫と言うたらえらい騒ぎになりますから、事業者が全部確認するのは当たり前だが、国がチェックするのはサンプリングだという話なんですね。国が全部確認するという話じゃないんですよ。
この前、当委員会で、原子力研究所、東海村、見に行きました。あそこでやっていたクリアランスというのは、原子炉規制法に基づくクリアランスですから、あの現場では、この積み上げているものはすべて国が確認するんですみたいなことをおっしゃっていましたけれども、今ここで法改正しようとしているのは、直接国が全量検査するわけでもないんですよね。結局、最終的には、形式的にチェックする、あるいはサンプリングでチェックするということになります。そうなりますと、すり抜けることがあり得るのではないかという問題を提起したいんです。
そこで、これも事実関係を、これも事務方で結構です、御報告いただきたいんです。
二〇〇三年三月に岡山県倉敷市で起こった事例、二〇〇八年十一月に福島県西白河郡西郷村、ここで起こった事例について御説明ください。
○泉政府参考人 まず、初めの二〇〇三年の方の件でございますけれども、これは、倉敷市の製鉄所で、放射性物質を含むスチールの缶をプレスしたブロックが見つかっておりまして、このブロックの放射線の線量率が表面で最大二十四マイクロシーベルト・パー・アワーでございまして、直ちに人体に影響を及ぼすものではなかったわけでございますけれども、このものを鉛の容器で封印いたしまして、放射線防護上必要な措置を施した上で、この原因物質の分析及び処分のために、日本アイソトープ協会の方に搬出がなされました。それで、このアイソトープ協会での分析によりまして、放射性物質は密封されたラジウム226であるということが確認されております。
それから、二〇〇八年の方の事例でございますけれども、これは、福島県の鉄くずリサイクル業者の工場内にございました砂状の物質から放射線が検出されたという連絡がありましたので、文部科学省では、この会社に対しまして、安全確保措置と専門の分析機関による分析を指導したところでございます。
分析の結果、この砂状の物質にトリウムが含まれているということが判明いたしましたので、文部科学省職員を派遣いたしまして、この砂状の物質が安全に保管されていること、それから、従業員に対する放射線障害のおそれがないこと、さらに、事業所の外に影響のないこと等を確認いたしまして、その上で、この会社に、原子炉等規制法に基づく核原料物質の使用の届け出を提出させるとともに、適切に管理するよう指導を行ったところでございます。
○宮本委員 この一つ目の事件、これは、製鉄所に空き缶をプレスしたものが運び込まれて、その中に放射性物質らしきものが発見されたという連絡があった。結論は、線量は少なかった、つまりこの影響は少なかったと言うんですが、物質そのものは、今おっしゃったように、ラジウム226という紛れもない放射性物質がプレス缶の中にまじっていたという事例であります。
二つ目の事例は、これも鉄のスクラップでありますけれども、鉄のスクラップの中から布袋に小分けされた砂状の物質が出てきて、これがトリウムを含む放射性物質であるということが明らかになった。
これは、これらの物質が発見された業者が悪いという話じゃないんですよ。この業者にそれを持ち込んだ者がおるわけです。空き缶を処理するところへこの放射性物質を紛れ込ませた、あるいは、鉄スクラップの処理工場へそういう放射性の砂状のものを持ち込んだ者がいるわけですよ。これはもう完全に取り扱いとしては間違っていると思うんです。
これは随分時間がたっていますけれども、だれがこれをこれらのところへ持ち込んだか明らかになっておりますか。
○泉政府参考人 お尋ねの点については判明いたしておりません。
○宮本委員 わからないんです。密封されているかどうか知らないけれども、スチール缶をプレスしたところへだれがこのラジウム226というものを出した犯人なのかはわかっていないわけです。それから、もう一つの福島県の例でも、鉄スクラップの中になぜトリウムを含んだような砂状物質が出されたのか、だれが出したのかはわかっていないんですよ。
だから、今度の法というのは、〇・〇一ミリシーベルト以下だったら大丈夫じゃないかという議論は、それは、〇・〇一ミリシーベルト以下は大丈夫ということに異論はありません。しかし、現状でも、一体だれが出したかわからないような形でこういう事例が起こっているわけですよ。
問題なのは、このように処理、再利用、つまりスクラップや何かに入ってしまった後では、だれが不法に投棄したのか廃棄したのかわからなくなってしまうということですよ。
先ほど、廃棄費用は、産業廃棄物なら百万円、放射性物質だったら二百六十万から一千万という話になりましたから、これはどう考えても、コストからいえば産業廃棄物として処理した方が安くつくわけですから、そういう不心得者が生まれてこないという保証はないわけですね。圧倒的多数の方々はまじめだとしても、中にこういう事件は幾らもあるわけですから、こういう点がそもそもチェックする体制がないのではないかということを私は指摘しているんです。
大臣、この点についての御所見をお伺いしたい。
○川端国務大臣 午前中の質問でもそうですが、いわゆるクリアランスの実施の方法とその測定の正確さのチェック、先ほど、サンプリングと全記録の検査と同時に、現地に赴いてそれをチェックするということで、二重三重の安全確認ということと同時に、これは、管理区域外へ出るという意味で、管理区域内にあるクリアランス適用外のものと混入するということは仕組みとしては排除する形をとっておりますが、先生言われたように、悪意を持って何とか紛れ込ませてやろうというものを完璧に全部とらえられるかどうかと言われれば、それは、どんな仕組みでもそれをチェックするということがかなうかどうかは議論のあるところであろうというふうに思います。
悪意を持ってそれは最後にぽこっとそこへ紛れ込ますことをすることまでということで、その代償措置として当然そういうことがあり得るということでの厳罰に処するという罰則規定があるということは、そういうことをやることが起こるということを基本的には考えて、やったら罰しますよという抑止力を働かせているというのが、理屈上はそういうことだと思いますが、制度的、仕組み的には、考えられる管理体制を非常に厳格にするということで、先生もそれが担保されるならばという、担保できるかどうかの議論は多分ここで今やっている話だと思いますが、万全を期すということで臨んでいるところでございます。
○宮本委員 いや、反対という態度を私どもの党はとってよかったという御答弁ですね。
悪意を持ってやる者がいた場合に、これを本当に防げるかどうかはわからないという答弁が大臣から出るとは思いませんでした。もちろん、罰則があって事後に罰則で処罰するにしても、紛れ込んでしまえば、先ほどの二つの例だってわからなかったじゃないですか、だれが出したのかは。
○川端国務大臣 私が申し上げたのは、そういう部分で、二重三重のチェックによって、過失であろうと悪意であろうと基本的には摘発できる、チェックできるようになっているけれども、本当に悪意を持って何とかごまかしてやろうという人まで全部パーフェクトに排除できるということじゃないということは、当然そういうものだと思うんですよ。だから罰則規定がある。
これは、過失においてもそういうことがあるということがなければ罰則なんて要らないということになるわけですが、そういう意味で申し上げたのであって、そういうことが基本的には起こらないという前提で制度設計をしているということだけは、誤解のないように申し上げておきたいというふうに思います。
○宮本委員 このクリアランスの制度が入れば、クリアランスの結果、放射性汚染物から除外されたものについては、国が安全であるというお墨つきを与えることになってしまいます。
事業者がやったことだとか、国は関係ないとか、悪意を持った者が悪意を持ってやった場合にはそれはちょっと無理でしょうとか、そういうふうにはならないんですね。そうである以上、安全であると広く国民に説明する責任は国にあるわけですし、そこに国がしっかり責任を果たす担保できる体制が必要だと言わなければなりません。
我が党は、改めてその点を直視して、制度そのもののあり方を根本から構築し直すべきだということをはっきり指摘をして、私の質問を終わります。
○田中委員長 これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。宮本岳志君。
○宮本委員 私は、日本共産党を代表して、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正案に対し、反対の討論を行うものです。
本法律案にはさまざまな改正点がありますが、主要な改正は、放射性同位元素等による放射性汚染物のクリアランス制度の導入です。クリアランスの基準とされる〇・〇一ミリシーベルト以下のものを放射性汚染物から除外することには一定の合理性があります。ただ、放射線、原子力に対する国民の不信、不安が広く存在しているし、そもそも放射線防護の観点からは、できるだけ人体に放射線を受けないことが望ましいのは明らかです。
問題は、クリアランス制度を実施する場合、国民の安全の観点から、放射能濃度の高い放射性汚染物が産業廃棄物として処分、再利用されることがないよう制度的に担保されているかどうかです。放射能濃度が高い汚染物が混入されてしまうことは、国民の安全を確保する点からは万が一にもあってはなりません。
本法律案で導入されるクリアランス制度を見ると、放射能濃度の測定の評価方法について国の認可を得れば、放射性同位元素を扱うあらゆる事業者がクリアランスの実施主体となることができます。質疑で明らかになったように、事業者は五千を超え、その管理能力、実態もさまざまです。いまだにみずから所持している放射性同位元素の種類、量でさえ正確に把握できていない事業者もいる現状で、すべての事業者に安易に任せることなどできません。
また、クリアランス結果の国による確認も、全量検査でなくサンプリング調査にとどまり、大半は書面で済まされ、形式的なものとならざるを得ません。このように安全確保に対する国の関与が限定的かつ形式的で、事業者任せの制度になっているのでは、放射能濃度の高い放射性汚染物が万が一にも産業廃棄物に混入しないという保証、担保がなく、国民の安全が確保されません。
本法律案には、放射線発生装置から発生する放射線による汚染物(放射化物)の規制の導入、輸出制限の緩和、罰則の強化など、現状に照らして必要であり、賛同できる部分もありますが、このようなクリアランス制度の導入は問題であり、全体としては反対せざるを得ないことを申し上げ、討論を終わります。