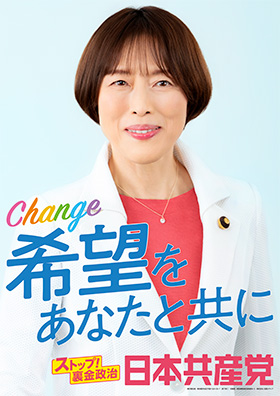平成二十二年四月八日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 池坊 保子君
理事 石井登志郎君 理事 小野塚勝俊君
理事 黒田 雄君 理事 佐藤ゆうこ君
理事 園田 康博君 理事 菅原 一秀君
理事 松浪 健太君 理事 高木美智代君
打越あかし君 大泉ひろこ君
大山 昌宏君 京野 公子君
小林 正枝君 斉藤 進君
玉城デニー君 道休誠一郎君
畑 浩治君 初鹿 明博君
室井 秀子君 山崎 摩耶君
山本 剛正君 柚木 道義君
和嶋 未希君 あべ 俊子君
小渕 優子君 馳 浩君
宮本 岳志君 吉泉 秀男君
…………………………………
国務大臣 福島みずほ君
内閣府副大臣 大島 敦君
内閣府大臣政務官 泉 健太君
総務大臣政務官 小川 淳也君
文部科学大臣政務官 高井 美穂君
厚生労働大臣政務官 山井 和則君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 松田 敏明君
政府参考人
(法務省民事局長) 原 優君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 香取 照幸君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房統計情報部長) 高原 正之君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 阿曽沼慎司君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 山田 亮君
衆議院調査局第一特別調査室長 湯澤 勉君
―――――――――――――
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
京野 公子君 和嶋 未希君
道休誠一郎君 畑 浩治君
初鹿 明博君 斉藤 進君
山崎 摩耶君 玉城デニー君
同日
辞任 補欠選任
斉藤 進君 初鹿 明博君
玉城デニー君 山崎 摩耶君
畑 浩治君 道休誠一郎君
和嶋 未希君 京野 公子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
青少年問題に関する件
――――◇―――――
○池坊委員長 次に、宮本岳志さん。
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。
まず冒頭、池坊委員長に一言申し上げたい。
私の反対を押し切って私の質問時間を五分間短くしたことは、断じて納得をしておりません。冒頭、抗議の意思をはっきり申し上げて、質問に入りたいと思います。
私も、この間の委員会視察に参加をいたしまして、改めて、日本の子どもたちと子育てをめぐる現状の深刻さ、立ちおくれを実感いたしました。
本来子どもにとって一番安全であり安心できる場所でなければならない家庭で起こる虐待、その背景には、貧困あるいは格差社会など、親も含む社会のありよう全体、これに大きな困難とゆがみがあると痛感をいたしました。
児童虐待防止法のもとでさまざまな対策が進められてきたわけですが、日本社会のありようという、その大もとの問題にメスが入らなければ、問題の根本的解決はないと思います。
そこで、まず、現政権のこの問題に取り組む姿勢について大臣に問いたいんです。
ことし一月二十九日に閣議決定された子ども・子育てビジョンでは、社会全体で子育てを支えることを掲げ、一人一人の子どもが幸せに生きる権利、育つ権利、学ぶ権利を大切にすると述べられております。これは、ただ単なる少子化対策として子どもを生み育てる責任の多くを親の扶養義務や家庭の自己責任に求めてきた今までの対策から、大きく一歩踏み出すものだというふうに思います。
社会全体で子どもと子育てを支える、これが現政権の基本姿勢だと認識をしておりますけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○池坊委員長 答弁者を指名いたします前に、宮本岳志さんからの今の御発言でございますが、質疑時間を決定いたしますのは、委員長の強権ではございません。理事会で決議したということをしっかりとここで、誤解ないように、委員の皆様方にも申し上げておきたいと思います。
それでは、福島国務大臣。
○福島国務大臣 おっしゃるとおりです。
子ども・子育てビジョンに関して、単に子どもが、私たちの将来の、例えば年金やいろいろな制度を負担してくれるからとか、少子高齢化が問題だからということだけではなく、もっともっと重要なことは、子どもは、その存在そのものが大事であって、本当に未来の存在であって、大事な存在であって、存在そのものを応援することが必要だというのが、おっしゃるとおり、子ども・子育てビジョンの骨格です。
だからこそ、チルドレンファースト、子どもを真ん中に置いて、子どもが主人公で、子どもの権利に関する条約を踏まえて、子どもを、子育てを応援していこう、そういう考えで子ども・子育てビジョンをつくりました。ですから、もちろんこれは、単なる少子化対策だけではないわけです。
子育ては、基本的には親が第一義的に責任を負うとしても、当たり前ですが、個人に過重な負担がかかったり、親だけで子どもを育てられるわけではもちろんありません。ですから、社会全体で子育てを支えて、個人の希望が実現できることを目指して、子どもを大切にする社会をつくるという観点からこのビジョンをつくりました。ですから、少子化対策から子ども・子育て支援へと視点を移し、当事者の目線で、子育てを社会全体で応援すると考えています。
子ども・子育て支援を進めるに当たって、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス、子ども・若者育成支援とも関係があるという認識を持っておりまして、そのさまざまな施策ともあわせて解決していきたいというように思っております。社会的な支援をしっかりやりながら、子育ての応援をしていきたいと思っております。
○宮本委員 私は、冒頭、私が納得していないということを申し上げたわけでありまして、そのことに抗議の意を表明したまでであります。
さて、そういう、社会で支えるということが求められているわけですけれども、現状は、まだまだ、子どもと子育てはその親の自己責任にのみ押しつけられて、思いがけない妊娠や望まれずに産み落とされた子どもが無残にもその命まで奪われるという、悲しい事件が後を絶ちません。
先日視察してきた熊本県の「こうのとりのゆりかご」、いわゆる赤ちゃんポストというものは、そういう現状に対する一つの鋭い問題提起だというふうに思います。
「「こうのとりのゆりかご」が問いかけるもの」という昨年十一月二十六日に熊本県が発表した報告書では、「ゆりかご事例から見えるのは、社会のありようの一面であり、現代社会の子育てにおいて個人や個々の家庭だけでは背負いきれないものが形として噴出している状況」だ、こう述べて、先ほど私が申し上げた問題意識と重なる認識を示しております。
その上で、この報告書では、匿名で相談でき、一時的に母子を匿名のまま緊急保護し、短期の入所も可能な設備を備えた施設が全国に整備され、そこを中心にネットワークが形成されることが必要だと指摘をしております。現場で日夜悪戦苦闘してこられた方々の実感に立った、非常に大事な指摘だと思うんですね。
そこで、厚生労働省に聞くんですけれども、国や自治体の責任で、妊娠、出産、子育てに悩んだり困難にぶつかったときに、いつでもだれでも、その場で専門的できめ細かい相談に乗ってもらえ、必要な支援を受けられる、そういう場やネットワークの形成、こういう取り組みの現状はどのようになっておるでしょうか。
○山井大臣政務官 宮本委員にお答え申し上げます。
まず、厚生労働省としては、各都道府県等とともに、出産や子育てに悩んでいる方が相談しやすい環境整備のため、児童相談所全国共通ダイヤル、〇五七〇―〇六四―〇〇〇の実施を平成二十一年十月からいたしております。
また、妊娠、出産についての医学的な相談や心の悩みに対応する女性健康支援センターの整備、これは、平成二十一年度におきまして三十七カ所、都道府県、指定市、中核市に整備をしております。
また、生後四カ月の子どもがいる家庭に保健師や子育て経験者が訪問し、子育ての不安や悩みの解消を図るとともに必要な支援を行う乳児家庭全戸訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業は、平成二十一年度、実施率が八四%であります。
また、市区町村においては、一般的に、助産師、保健師が妊産婦、新生児等の家庭を訪問しての相談や保健指導、また、市町村保健センター等における妊娠、出産、子育てに関する相談や保健事業などを行っております。
○宮本委員 熊本の「こうのとりのゆりかご」の視察で、祖父母が赤ちゃんを預けに来た例で、後で理由を尋ねたら、娘の戸籍を汚したくなかったと語ったという、本当にやりきれない話もお伺いをいたしました。
思いがけない妊娠ということになれば、まだまだ、妊娠、出産の段階から周囲に反対されたり白眼視されるということも多いと思うんですね。そうなれば母親は、子育ての最初から家族の中や地域で孤立しやすい状況に置かれます。そうした孤立が、子育ての不安や焦燥感を高めて、虐待のリスクを高めるという指摘もございます。
この問題は、熊本県のこの報告書も指摘しているとおり、日本社会のありようと深くかかわる問題であり、現代社会の子育てにおいて、もはや個人や個々の家庭だけでは背負い切れないものが厳然と存在していることは何人たりとも否定できない、そういう状況だと思っています。
さて、そういう前提を置いた上で、次に、児童虐待防止対策についてお伺いしたいと思うんです。
児童虐待防止法が施行されて十年、家庭内の問題だとかしつけなどということを口実にして子どもを虐待することは絶対に許されてはならない、こういう考え方がやっと浸透してまいりました。
しかし、先日も、東京江戸川区で、本人からの申告や歯科医師からの通告があったにもかかわらず、子ども家庭支援センターも学校も状況認識が甘かったことが一つの理由になって、ついに命を落とすという悲しい事件が発生をいたしました。
また、同居している男性による暴力で二歳の男の子が亡くなった大阪門真市の事件、あるいは、子どもをごみ箱に長時間閉じ込めて窒息死させたという事件、本当に胸の痛む事件が後を絶たないわけであります。
まず、これは大臣の認識をお伺いするんですが、政府として、この現状をどのように見ておられますか。
○福島国務大臣 おっしゃるとおり、児童虐待については、児童虐待防止法ができた以降、むしろ通報件数もウナギ登りにふえておりまして、また報道でも、子どもが命を失ってしまうという事件が相次いで、これは本当に喫緊のとても重要な課題だというふうに思っています。
このためには、やはり、ネットワーク力や対応が弱いということは、政治としてはっきり自覚すべきだと思います。これはもちろん、児童相談所が満杯状態だったり、家庭支援センターが、職員がとても忙しいとか件数を抱えているとか、なかなか親の親権に対抗できないとか、学校が家になかなか踏み込めないとか、さまざまな問題があるわけですが。
私は、一点、DVや児童虐待の認識についての研修やソーシャルワーカーの力が必要だと思います。
DVをする男性も、女性もいるかもしれませんが、あるいは児童虐待をしがちな親も、もう二度としないと言ったり、いや、しつけをしているんだとか、悪いことはしていない、殴ってなんかいないと必ず言うんですね。にもかかわらず、問題が続くというか、しつけや、いや、ちょっと手を出しただけだと言われていることが重いということを、そういう発言を聞いたら逆に危ないんだということを認識してやっていくだけの専門家集団のフォローアップが必要だと考えています。
○宮本委員 そういう状況のもとで、やはり体制が全然足りない。先ほどもそういう議論がございましたね。
いただいた資料によると、児童虐待防止法が施行された十年前、一九九九年度の相談件数は一万一千六百三十一件、十年後には、二〇〇八年度で四万二千六百六十四件と三・七倍にふえたということですけれども、先ほども指摘があったように、児童福祉司の方は、二〇〇九年四月一日の時点で二千四百二十八人と、正確に言えば、十年前の二倍にも達していないわけです。一人の児童福祉司が受け持つ虐待に関する件数は、平均で年間百件を超えるという事例も珍しくありません。
そもそも、この配置基準というのは児童福祉法施行令で定められておりますけれども、これは、もちろん子どもの数や交通事情を考慮するということはついているんですが、あくまで人口当たりの人数で定められているわけです。おおむね五万人から八万人までというふうになっております。そして、先ほど総務省の答弁もありましたけれども、地方交付税の算定による基準の方も、百七十万人当たり三十人、これも、割ってみたら、六万人弱ということになりますよね。
それで、私は、実は国立国会図書館で欧米各国の事例を調べていただいたんですね、欧米各国でどうなっているか。
ここにイギリスの例を持ってまいりましたけれども、イギリスでは、自治体の児童サービス部には国家資格を持つソーシャルワーカーが配置をされております。配置人数は各自治体が決定するんですけれども、一人当たりの平均的な担当件数というものは、児童虐待チームでは十件から十五件、家族委託チームでは十五件から二十件である、これが国会図書館の御説明でありました。児童福祉司の行う業務は極めて専門的でありまして、十五件とか二十件というふうにしておるのは、なぜかといえば、専門実務を行うことが可能である範囲にすることを原則にしていると。これがイギリスの制度のようです。
日本でも、もちろん専門的な仕事でありますし、ですから、私は、いつまでも人口基準のみでこの配置を決めるんじゃなくて、やはり一人当たりの相談件数、受け持ち件数を基準として明確に示す、抜本的な増員を図るべきだというふうに思うんですけれども、福島大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○福島国務大臣 児童福祉司さんがもっとふえて子どもたちをしっかり見るようになれば、随分これも変わっていくと思います。
青少年育成や少子化対策を担当する大臣として、児童福祉司の人員の確保や質の向上など、児童相談所自体の体制を充実させる方向で検討が進められるよう、やっていきたいと思います。
○宮本委員 二〇〇五年二月に、厚生労働省は、今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会、こういうものを設置いたしまして、二〇〇六年の四月に報告書が出されております。
それで、この報告書の「児童相談所の必要な職員体制の確保」という部分、児童福祉司の第一項ですね。ここでは、今後、国は配置基準についてどういう要素を基準として示すべきだと書かれてあるか、厚生労働省政務官からお答えいただけますか。
○山井大臣政務官 児童福祉司の配置基準のところでよろしいですか。
そこに関しましては、御質問の児童福祉司の配置基準については、児童福祉法施行令第二条において、保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね五万人から八万人までを標準として定めると規定されております。(宮本委員「それはもう終わったんです」と呼ぶ)いや、ですから、確認をしたんです。
○宮本委員 それは、既に先ほども私申し上げました。
ですから、厚生労働省が置いた、この研究会報告では、基準についてどのように示すべきだと述べられておりますかと聞いたんです。
○山井大臣政務官 御質問の点については、「今後、各都道府県は、政令改正も踏まえ、また相談内容なども加味しながら、より一層、児童福祉司の配置を充実させることが望まれる。 その際、相談件数や児童福祉司の担当事例件数、児童数など、人口以外の要素を基本とした標準について、国で示すべきである。」とまとめております。
○宮本委員 先ほど私が指摘したとおり、担当事例件数、児童数など、人口以外の要素を基本とした標準について国で示すべきだ、こういう指摘もされているわけですね。
これは、やはり本気でやらないと、幾ら、社会全体で子育てを支えるとか、一人一人の子どもが幸せに生きる権利、育つ権利、学ぶ権利を大切にすると子ども・子育てビジョンに書き込んでも、それは担保されないということになりますから、ぜひしっかりとこの見直しは進めていただきたいというふうに思います。
児童養護施設は、子どもの最後のセーフティーネットとして極めて重要であります。
二〇〇七年の十一月二十二日に出された社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会の報告書、「社会的養護体制の充実を図るための方策について」では、明確に、子どもにとって必要なケアの質を確保するための人員配置基準の引き上げや措置費の算定基準の見直し等を含めたケアの改善に向けた方策を検討することを求めております。
そして、先日、本委員会で視察に伺った熊本の慈愛園乳児ホームの施設長も、これは委員長の視察報告にもあるように、乳幼児一人に対する看護師、保育士等の人員配置基準を一人に引き上げること、また、一時保護に係る委託費の単価の引き上げなどに関する要望が出されました。
既にこの点についての検討に入っておられると聞いておるんですけれども、一体いつまでに結論を出して、この基準を見直すのか、お答えいただけますか。
○山井大臣政務官 お答え申し上げます。
御指摘のように、平成十九年十一月の社会保障審議会の社会的養護専門委員会の報告書において、子どもの状態や年齢に応じた適切なケアの実施のための施設類型のあり方や、人員配置基準、措置費の算定基準の見直しが必要、そのための必要な財源の確保や施設内のケアの現状についての詳細な調査、分析が必要と提言されました。
それを受けて、平成二十年三月に、全施設を対象に、施設の概況、入所児童の状態、背景等を把握することを目的とした調査を実施し、そして昨年の平成二十一年一月から三月に、子どもの状態によるケアの内容を定量的に把握するため、いわゆるタイムスタディーを実施してきたところであります。
また、現在、その詳細な分析、集計を行っているところでありまして、その結果等を踏まえ、社会的養護専門委員会で具体的に議論していただく予定になっております。
ついては、新たな次世代育成支援のための包括的・一元化システムについては、平成二十三年通常国会、来年の通常国会に法案を提出し、必要な準備を行い、先ほど申し上げましたように、子ども手当、そして保育所や学童クラブの整備、さらにこの社会的養護というものを三つの柱として新しいシステムの構築を図りたいと考えておりますので、社会的養護にかかわります施設機能の見直しについても、この新システム構築の全体的なスケジュールの中を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
○宮本委員 本委員会でも、児童養護施設の施設最低基準、これは見直しを繰り返し求めてまいりました。最低基準ができてもう既に六十年ということでありますから、やっと検討に入ったことは評価しつつも、やはり本当に急いでいただかないと、遅きに失した感は否めないと思います。
児童養護施設関係者らが求めているように、子どもの心のケアを充実させるなど個別の支援が可能となるような職員配置、個室の設置など、子どもの発達を保障する生活環境の確保、施設に入所している子どもたちの立場に立った見直しを進めていただきたいと思います。
最後のテーマなんですが、政府が今国会に提出しているいわゆる地域主権法案にかかわって、児童自立支援施設の職員資格の制限緩和ということについて伺いたいと思います。
まず、確認をしたいんですけれども、児童自立支援施設、この施設はどのような目的を持った施設なのか、入所してくるのはどのような子どもたちなのか、厚労省、お答えいただけますか。
○山井大臣政務官 お答え申し上げます。
児童自立支援施設とは、不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設であります。
以上です。
○宮本委員 自立支援という名称がつきますので、障害者の施設だと思っている人もおるようでありますけれども、この施設が児童自立支援施設と名前が変わったのは一九九八年の四月からでありまして、それ以前は教護院と呼ばれていた施設であります。
ここには、非行を行った児童が都道府県知事の判断で入所しているだけでなく、少年法に基づく家庭裁判所の保護処分決定に従って入所措置がとられる場合があるなど、その性質上、管理的な性質が高い施設でありますし、児童の処遇の難しさから、児童の権利擁護の観点も含めて高い専門性が必要となる施設だとされております。
それだけに、児童自立支援施設で子どもたちと日々向き合っている職員の資格は児童福祉法施行令三十六条に定められておりまして、第五項は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員は、当該都道府県の職員をこれに充てるとしております。
ところが、政府は、昨年十二月の地方分権改革推進計画で、この施行令三十六条五項は廃止すると決定をいたしました。一体、この理由は、なぜですか。
○山井大臣政務官 お答え申し上げます。
今回の見直しは、地域主権改革の実現に向け、法制的な観点から地方自治体の自主性を強化し、地方自治体がみずからの責任において行政を展開できる仕組みを構築するという地方分権改革推進委員会の第三次勧告の趣旨を最大限尊重したものであり、一律に児童自立支援施設の運営の民間委託を禁止していたものを改め、地方自治体がみずからの責任において民間委託を選択することも可能としたものであります。
宮本委員御指摘の点は、私も非常に重要な論点だと当然思っております。ですから、このことによって、当然、ケアの質といいますか、そういうことが下がることがあっては決してならないというふうに思っております。
○宮本委員 それは、当然のことなんですよね。ケアの質が下がることはあってはならないというのはもちろんなんですけれども。
今お話があったように、全国知事会からも、実はこの規制緩和を求める意見が出されてまいりました。その中身は、この三十六条五項があると児童自立支援施設の外部委託が不可能なために、それで、効率的な行政運営が可能となるよう職員の身分規定を廃止すべきという要求があったというんですね。つまり、コストの削減をしたいというのが知事会の要求だと思います。
しかし、この児童自立支援施設の民営化問題をめぐっては、二〇〇五年七月に厚労省自身が設置をして、二〇〇六年二月に報告書を取りまとめた児童自立支援施設のあり方に関する研究会というものがやられておりまして、ここで議論をされてきた経緯がございます。
まず、冒頭、これは厚労省に確認いたしますけれども、児童自立支援施設のあり方に関する研究会の報告、ここに持ってきましたけれども、この報告については、厚労省は尊重いたしますね。
○山井大臣政務官 当然、尊重いたします。
○宮本委員 尊重するということであります。
この報告書では、さまざまな角度からの検討がやられております。そして、この中では、児童自立支援施設が、極めて公共性の高い施設であり、子どもに対する適切な対応を図っていくためには、施設運営の安全性、安定性、継続性に加えて、職員の専門性の確保が不可欠だと強調した上で、施設の民営化を検討の視野に入れる場合には、少年非行対策へのスタンス、公としての責任、対応、民営化する場合の施設機能の維持強化などの検討が必要であり、特に、財政的基盤のあり方、現行と同等以上の支援の質を確保するための人的配置、公的支援・連携システム、とりわけ、運営に支障が生じた場合の設置者としての責任を持った回復サポート体制などの諸課題を満たすことができるかどうかについて検証が不可欠だ、こう述べているわけですね。
では、この研究会報告書に基づいて、今述べたようなことをきちっと検討、検証いたしましたか。
○山井大臣政務官 宮本委員にお答えを申し上げます。
規制緩和や民間委託によってケアの質が落ちてはならない、これは当然のことであります。現在の鳩山政権においては、地域主権ということを進めてまいりますが、これは当然の前提だというふうに思っております。
ですから、今回の民営化におきましても、民間委託が可能になっても、処遇にかかわる高い専門性が損なわれることはあってはならないということを考えておりますし、そうするための方策として、先ほど御指摘いただいた児童自立支援施設のあり方に関する研究会の報告書も尊重をしてまいりたいと思っております。
また、児童自立支援施設の民間委託を地方自治体が検討する場合には、研究会の報告書で指摘されているように、今、宮本委員がおっしゃいましたように、財政基盤のあり方、人的配置、公的支援・連携システムなどの諸課題を満たすことができるかどうかについて検討をいただくことが必要だというふうに考えております。
厚生労働省としても、地方自治体の自主性を尊重しつつ、引き続き、児童自立支援施設における支援の質の確保について、有識者や関係者の御意見も伺いながら、検討し、地方自治体に助言してまいりたいと思います。
改めて申し上げますが、今回のことによってケアの質がアップすることはあっても低下することがあってはならないと考えております。
○宮本委員 民間委託をするときに検討することはもちろんでありますけれども、十二月のこの閣議決定をするに当たって、きちっと、民営化を視野に入れる場合にも検証が不可欠だと指摘された中身を、国は、厚労省は検証いたしましたかと聞いたんです。
○山井大臣政務官 繰り返しになりますが、これに関しましては、自治体が民間委託をする際に、この報告書の趣旨を尊重して、財政基盤のあり方、人的配置、公的支援・連携システムなどの諸課題を満たすことができる、そのことを検討する。逆に言えば、満たすことができないのであれば、それは民間委託にふさわしくないということになると考えております。
○宮本委員 この検証、検討というのは全くされていないんですよね。やっておられないですよ。
私、ここに全国児童自立支援施設協議会が長妻厚労大臣あてに出した意見書というものを持ってまいりました。
昨年の二月に、この協議会の役員会に厚労省の担当官が出席し、この問題についての検討会を設置する旨の説明があった、にもかかわらず、こうした検討や検証を一切捨象して、公設民営化への道を開く第三次勧告、そしてこの計画が出されてきたんだ、これは遺憾であり、とても容認できるものではないと、はっきり述べておられるんですね。
ですから、大臣も閣議決定に参加されたと思うんですけれども、これは本当に、現場の人の意見に照らしても、おかしいんじゃないですか。大臣、そう思われませんか。
○福島国務大臣 宮本委員おっしゃるとおり、民営化という中での問題点の指摘や懸念は理解できるところです。
今、山井政務官が申し上げたとおり、民営化が可能となっても、質が落ちたり、ケアが必要な入所や処遇困難なケースを取り扱うことがあるわけですから、それに対する専門性の確保や質の確保がない限り民営化はできないということを、青少年育成担当大臣として、地方における取り組みを注視し、監視してまいります。
○宮本委員 研究会報告書の結論は、以上を踏まえ、児童自立支援施設は、子どもの健全な発達、成長のための最善の利益の確保を目指し、取り組むべき課題について取り組めと、こう言っているわけですよね。
だから、知事会が言うように、いかにコストを削減するかという視点からではだめであって、子どもの最善の利益をちゃんとしっかり追求せよというのが研究会の報告書ですから、やはりその立場でしっかり見ていく必要があると思います。
私は、この協議会の方々にも委員会に参考人として御参加いただいて、ぜひとも御意見も伺ってみたいと思っております。
以上で、時間が参りましたので、私の質問を終わります。