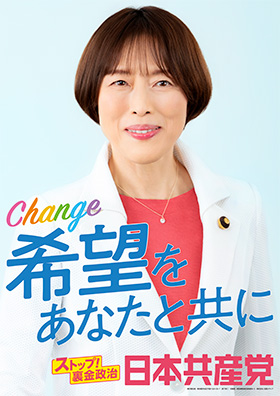就学援助制度の充実を 宮本議員要求 (動画あり)
平成二十二年二月十八日(木曜日)
午後三時一分開議
出席委員
委員長 鹿野 道彦君
理事 池田 元久君 理事 岡島 一正君
理事 海江田万里君 理事 伴野 豊君
理事 松原 仁君 理事 山口 壯君
理事 加藤 紘一君 理事 町村 信孝君
理事 富田 茂之君
磯谷香代子君 今井 雅人君
打越あかし君 小野塚勝俊君
緒方林太郎君 岡本 充功君
奥野総一郎君 笠原多見子君
城井 崇君 黒田 雄君
古賀 一成君 近藤 和也君
田中 康夫君 津島 恭一君
豊田潤多郎君 中林美恵子君
長島 一由君 野田 国義君
畑 浩治君 平岡 秀夫君
三谷 光男君 水野 智彦君
山田 良司君 吉田 公一君
若泉 征三君 渡部 恒三君
金子 一義君 小池百合子君
下村 博文君 菅 義偉君
田村 憲久君 橘 慶一郎君
谷 公一君 谷畑 孝君
山本 幸三君 石田 祝稔君
大口 善徳君 笠井 亮君
宮本 岳志君 吉泉 秀男君
柿澤 未途君 山内 康一君
下地 幹郎君
…………………………………
財務大臣 菅 直人君
総務大臣 原口 一博君
外務大臣 岡田 克也君
文部科学大臣 川端 達夫君
農林水産大臣 赤松 広隆君
経済産業大臣 直嶋 正行君
国土交通大臣 前原 誠司君
国務大臣
(内閣官房長官) 平野 博文君
国務大臣
(金融担当)
(郵政改革担当) 亀井 静香君
国務大臣
(国家戦略担当) 仙谷 由人君
財務副大臣 野田 佳彦君
総務大臣政務官 小川 淳也君
総務大臣政務官 長谷川憲正君
外務大臣政務官 吉良 州司君
財務大臣政務官 古本伸一郎君
予算委員会専門員 杉若 吉彦君
―――――――――――――
委員の異動
二月十八日
辞任 補欠選任
打越あかし君 野田 国義君
梶原 康弘君 今井 雅人君
沓掛 哲男君 近藤 和也君
黒田 雄君 水野 智彦君
平岡 秀夫君 磯谷香代子君
森本 和義君 笠原多見子君
小里 泰弘君 橘 慶一郎君
谷川 弥一君 谷 公一君
大口 善徳君 石田 祝稔君
笠井 亮君 宮本 岳志君
阿部 知子君 吉泉 秀男君
山内 康一君 柿澤 未途君
同日
辞任 補欠選任
磯谷香代子君 平岡 秀夫君
今井 雅人君 梶原 康弘君
笠原多見子君 森本 和義君
近藤 和也君 沓掛 哲男君
野田 国義君 打越あかし君
水野 智彦君 黒田 雄君
橘 慶一郎君 小里 泰弘君
谷 公一君 谷川 弥一君
石田 祝稔君 大口 善徳君
宮本 岳志君 笠井 亮君
吉泉 秀男君 阿部 知子君
柿澤 未途君 山内 康一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成二十二年度一般会計予算
平成二十二年度特別会計予算
平成二十二年度政府関係機関予算
――――◇―――――
<国際人権規約A規約十三条の2の(b)と(c)高校・大学等の漸進的な無償化を留保しているのは日本とマダガスカルだけ>
○鹿野委員長 これにて石田君の質疑は終了いたしました。
次に、宮本岳志君。
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。
きょうは、教育の無償化と教育格差の問題をお聞きしたいと思っております。
総理は、施政方針演説で、すべての意志ある若者が教育を受けられるよう、高校の実質無償化を開始しますと述べ、国際人権規約における高等教育の段階的な無償化条項についても、その留保撤回を具体的な目標とし、教育の格差をなくすための検討を進めますと述べられました。これは当然のことだと思っております。
国際人権規約、すなわち、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約を、我が国は一九七九年に批准いたしましたけれども、その十三条の2の(b)と(c)については批准を保留したまま今日に至っております。(b)というのは中等教育の無償教育の漸進的な導入をうたったものであり、(c)とは高等教育の無償教育の漸進的な導入をうたったものであります。
既に、国際人権規約のA規約については百六十カ国が批准をしているはずでありますけれども、まず、確認の意味で外務大臣に、この十三条二項の(b)、(c)の批准を留保している国はどの国か、お答えいただけますか。
○岡田国務大臣 委員御指摘の、いわゆるA規約十三条の2(b)及び(c)の規定でありますけれども、ここを留保している国は日本とマダガスカル、二国のみであります。
○宮本委員 これまで長く、ルワンダ、マダガスカル、日本の三カ国がこの条項を保留してきたんですけれども、ついにルワンダが一昨年十二月に留保を撤回いたしまして、残るは日本とマダガスカルのわずか二カ国のみとなりました。二カ国で最下位争いをしているという、経済大国と言われる日本が非常に恥ずかしい限りだと言わなければなりません。
この人権規約の所管は外務省でありますけれども、総理が、「留保撤回を具体的な目標とし、」こう施政方針演説で述べた以上、外務省として具体的にいつまでにこの留保を撤回するのか明確にすべきだと思いますけれども、外務大臣に、留保撤回に向けての具体的なめどをお尋ねしたいと思います。
○岡田国務大臣 まず、十三条2の(b)に規定する中等教育のうちの後期中等教育、すなわち日本で言う高校教育でありますけれども、この点については、鳩山内閣として高校実質無償化法案が提出されておりますので、外務省としては、そのことを受けて、同法案と我が国が規定上負う義務との関係について現在精査しているところであり、本件規定に付している留保の撤回につき検討しているところであります。
具体的には、やはり法案が成立するということを見定めた上で、留保について働きかけといいますか、撤回を行いたいというふうに考えているところであります。
それからもう一つの大学教育につきましては、現在、これも鳩山内閣として経済的負担軽減策を文部科学省が検討しておりますが、そのことが、同規約十三条の2の(c)に規定する義務との関係について精査の上、本件規定に付している留保の撤回の可能性について検討していきたいというふうに考えているところでございます。
○宮本委員 この人権規約の留保撤回については、昨年の臨時国会でも議論がございました。昨年の十一月の十八日、文部科学委員会で川端文部科学大臣から、私は留保撤回に向けて検討を進めるという御答弁をいただいた。数日後には外務委員会で、岡田外務大臣からもそういう御答弁がございました。
ところが、昨年の年末に外務省が国連に出した政府報告を見て私は驚いたんです。この問題についての国連に出した政府報告では、「無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保していると、実は、自公政権時代と全く変わらない回答を昨年末の時点でしたわけですね。
今お話をお伺いし、総理の施政方針演説を聞きましたら、これは去年の年末の時点の話であって、今やこの立場ではないと。つまり、この報告の状況はもう既に否定されていると私は理解をするわけですけれども、それでよろしいでしょうか。
○岡田国務大臣 今委員御指摘の件については、昨年の十二月二十二日に、いわゆるA規約の第三回政府報告を国連事務局に提出したところでございます。
この報告につきましては、第二回政府報告提出後の一九九八年八月から二〇〇九年四月時点のことについて報告をしておりまして、同時に、この報告をするときに、二〇〇九年九月に新政権が成立しており、同報告の幾つかの項目について再検討を開始しているというふうに明記したものでございます。
二〇〇九年四月以降の新たな動きにつきましては、今後、政府報告審査のためにA規約委員会から出される質問事項への書面回答、あるいは、来年以降に予定される政府報告審査において追加的に説明するという予定にしております。
よって、そういった、期間が限定されて、それに関しての報告ということでありましたから、今御説明申し上げたようなことになっておりますけれども、先月、鳩山総理の施政方針演説があり、その中で、国際人権規約における高等教育の段階的な無償化条項についても、その留保撤回を具体的な目標とするというふうに明確に述べられました。
現在の政府の考え方はこの鳩山総理の施政方針演説でありますので、そういう方向にのっとってさらなる努力をしていきたいというふうに考えているところでございます。
○宮本委員 この報告書を見せていただくと、実は、新しい政権成立後に文言が変わったものもあるんですね。例えば二十ページに、年金について同じように国連に答えた文面があるんですが、「最低保障年金については、二〇〇九年九月の「連立政権樹立に当たっての政策合意」において、最低保障年金を含む新たな年金制度を創設することとされている。」とちゃんと書き込んだものもあるんですよ。ところが、この漸進的無償化条項の留保撤回については、旧来の政権のまま、何ら変わりがないわけですね。
これは私、各省庁とも相談の上で外務省は作成したというふうにお伺いしましたけれども、ちょっと文部科学大臣、なぜ教育の無償化条項だけはこういうふうに最低保障年金のように書きかえなかったのか、お答えいただけますか。
○川端国務大臣 今、外務大臣が答弁いたしましたように、最終的には、この国のそのときの政権の状況を判断して、外務省の責任において精査の上報告されたものと承知をしております。
○宮本委員 やはり総理がそういう施政方針演説ではっきりと示されているわけですから、これは直ちに留保撤回の意思をしっかり表明すべきだというふうに思います。
そもそも、国際人権規約の十三条二項(b)、(c)という規定は、これは漸進的無償化条項と呼ばれるものであって、つまり、段階的に、徐々に無償化を目指すということを定めた条項であって、岡田外務大臣が御答弁のように、既に高校無償化法案については今国会に提出をされました、もちろん成立はまだですけれども。ですから、(b)項を留保しておく理由はもはやないと言わなければなりません。そして、高等教育の(c)項についても、総理が施政方針演説で高等教育の段階的な無償化を目指すと明言したわけですから、これは留保は撤回できるはずだと思うんですね。
外務省にも確認しましたけれども、何か国連から問われたものに対する報告の機会にだけ撤回できるんじゃなくて、撤回しようという気になれば、いつでも日本の政府が国連に申し出ることはできるんだということでありますので、今国会中にはやはり踏み出すべきだと思いますが、外務大臣、いかがでしょうか。
○岡田国務大臣 これは、どのぐらい厳密に物事を考えるかという問題でもあると思います。ですから、法案とか予算というものが、まさしくこの予算委員会で予算が審議されており、そして法案もこれから国会の中で議論されるというときに、それを先取りして言うべきかどうか、そういう問題でもあると思うんですね。
この国会中にというふうに委員言われましたが、この国会中にそういった予算が成立をし、そして法案がきちんと成立をするということになれば、これは直ちに撤回について求めることはできるというふうに考えております。
○宮本委員 ぜひそういう方向で踏み出していただきたいということを申し上げたいと思います。
それで、漸進的な学費無償化に向かう上で、おっしゃるとおり、問題は大学なわけです。今、日本の大学生は世界一高い学費に悩まされ、学問よりアルバイトに追われるという生活を余儀なくされております。学生生活が深刻だという話をよく聞くわけであります。
川端文部科学大臣は、私の質問に対して、留保撤回に向けた施策について検討を進めたい、こういう御答弁をいただきました。学費の免除の拡大や返済の必要のない給付制奨学金の導入、こういうことが抜本的な対策として求められると思うんですけれども、ひとつ、高等教育、大学の留保撤回に向けての具体的な施策、これは川端文部科学大臣にお答えいただきたいと思います。
○川端国務大臣 先ほど来出ておりますように、総理の施政方針演説においてこの撤回に向けて検討を進めていくということの中で、具体的な対応として、私たちは、いわゆる大学授業料の減免と、それから奨学金事業の拡充ということを二つの大きな施策と考えております。
具体的に申し上げますと、この御審議いただいている二十二年度予算においては、一番目としての授業料減免措置は、国立大学では、対前年比十四億円増の百九十六億円を計上し、免除人数を約五万人から五千人増の五万五千人、免除率が五・八%から六・三%に拡充、私立大学は、対前年度二十億円増の四十億円を計上し、約二・八万人から約三万人に拡充、合わせて八万五千人に拡大。そして公立大学は、地方でございますので、地方財政措置を通じて支援をしていきたいと考えております。
また、大学の奨学金に関しては、対前年度五百八十億円増の一兆五十五億円の事業費を計上し、貸与人員で三万五千人増の百十八万人に拡大を予定いたしております。
諸施策を拡充する中で、この(c)項の留保が撤回されるように、外務省の精査を待ちたいというふうに思っております。
以上です。
<教育費の負担は授業料だけではない>
○宮本委員 しっかりと進めていただく必要があるんですが、やはり、奨学金について言いますと、日本は給付制のものが本当にないんですね。返さなきゃならない。しかも、圧倒的に有利子ということになっておりますので、ぜひ給付制の奨学金を実現するために全力を尽くしていただきたいと思っております。
それで、次の質問に進みますけれども、義務教育については無償とする、これは言うまでもなく憲法二十六条の規定であります。先ほど(b)項、(c)項の留保について問題にしましたけれども、この十三条2の(a)項というのは義務教育の無償化、これは国際人権規約に定められておりまして、これについてはもちろん我が国も批准を既にしているわけです。
ところが、この義務教育の無償というものも、実は、無償といいながら、実態的には無償ではないという現状があるわけですね。
先日、文部科学省による平成二十年度の子どもの学習費調査というものが公表されました。きょうは、資料一におつけしてございます。この資料を見ますと、これによると、公立の小学校で学校教育費が平均で年間五万六千二十円、公立中学校で平均十三万八千四十四円かかっていることが明らかになっております。
この学校教育費というものは何を指すのか、具体的に文科大臣にお答えいただきたいと思います。
○川端国務大臣 お答えいたします。
学校教育費の内訳の項目を申し上げますと、修学旅行・遠足・見学費、学級・児童会・生徒会費、PTA会費、その他の学校納付金、寄附金、教科書以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、その他の十二項目でございます。その他とは、今申し上げた学校教育費の内訳のいずれにも属しない経費で、学校の記章・バッジ、上履き、卒業記念写真・アルバムの代金等というふうにしております。
○宮本委員 これは、給食費を除いた、今おっしゃったような学用品、教科書以外の図書費などですね。
ここに、山口県のある小学校五年生の学級会計報告を持ってまいりました。資料二におつけをしてあります。
四月の集金として二千円、五月集金分として二千円、六月は別紙で、社会見学集金として千四百円、そして七月はもとの会計報告に戻って千二百円が徴収をされているわけです。それで、支出の部を見ると、国語テスト二百八十円、社会テスト二百八十円、算数テスト二百八十円、漢字ドリル三百三十円、社会科資料集五百九十円、音楽ワーク三百七十円、粘土三百九十円、夏休み帳三百九十円、家庭科実習費百円、色画用紙九円、画用紙等々となっております。
教育活動がこうした学校教育費の徴収によって成り立っているということがはっきりとわかります。
大阪の八尾市のある小学校では、教材費として、一年生から六年生まで八万七千七百九十円徴収されている。その支出内容を見ると、副読本、歌集、ドリル、市販のテスト類に加えて、アサガオセットとか土、肥料、苗、種、工作キット類、実験セット類、調理実習材料、調味料、版画用インク、ニス、はけ類、ざら紙、半紙にまで支出をされております。そして、積立金が四年生から始まって三万一千九百円が徴収され、修学旅行費やアルバム代や卒業制作費となっております。
高校の授業料の無償化を進めて、実質無償化だと言うんですけれども、現実には義務教育ですら実質は無償でなく、こういう大きな父母負担によって成り立っているわけですね。文科大臣、この実態をこのままでよいとお考えかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
○川端国務大臣 お答えいたします。
御指摘のように、憲法第二十六条で「義務教育は、これを無償とする。」と規定されておりまして、国公立学校における義務教育については、授業料を徴収しないこととしております。また、義務教育諸学校においては、教科書を無償で貸与しております。そういう中で、いろいろ費用がほかにかかることは現実としてございます。そして、学校によっても違います。
そういう中で、学校教育法第十九条において、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないという法的な保障を定めておりまして、そういう意味での低所得者層に対しては、保護者による私費の負担の軽減を図っております。
この規定に基づいて、市町村が主体でございますので、要保護及び準要保護児童生徒に対して、学用品、修学旅行費、学校給食費等の援助を実施しているのが現状でありまして、国においては、この要保護者に対して市町村が就学援助を行う場合に二分の一の援助をするという仕組みでありまして、今の仕組みの中ではこういう実態であるということを申し上げたいというふうに思います。
○宮本委員 八尾の事務職員の方に聞きましたけれども、毎年、市の配分予算にマイナスシーリングがかけられてくるので、できる限りこういった教材費も公費負担をしたくても難しい、毎年、未納家庭が多くなるのに市の予算が減らされては悪循環になるばかりである、何のための義務教育無償なのかわからない、そういう声をお聞きいたしました。
私は、国立国会図書館で調べていただいたんです。諸外国ではこうした教材や教育活動にかかる費用は無償なんですね。イギリスでもアメリカでも、ドイツやフランスでもカナダでも、皆無償ですよ。学力世界一のフィンランドでは、給食も含めて無料で行われております。
我が国の現状は、子どもの貧困白書、こういうものを見てみても、入学時に必要な義務的経費は、小学校一年生で十三万三千四百八十五円、中学校一年生では約二十五万六千円かかるというデータが示されております。
こういう私費負担をやはり軽減する方向で努力すべきだと私は思うんですが、文部科学大臣、もう一度お答えいただけますか。
○川端国務大臣 先ほど申し上げましたように、今の制度としては、家計の厳しいところに一定の応援をさせていただくという仕組みで動いております。
このことを通じてには一定の限界があることも、ニーズがたくさんあることも承知をいたしておりますが、そういう中で、トータルとして、学校教育ということの肩がわりという意味ではなくて、加えて応援するという意味での施策としての子ども手当等の考え方で手当てするということも、総合的な内閣の政策としては実施しているところでありまして、今のところ現行の制度でやらせていただいている、現状は承知をいたしておるというのがお答えでございます。
○宮本委員 先ほど就学援助についても触れられましたし、今も答弁がございました。そういった大変な保護者の負担を救う命綱ともいうべきものが就学援助であります。ところが、その命綱も切られようとしているという現状があるということを、これは残念ながらお示しせざるを得ません。
こうした教材費などが払えない家庭に対する就学援助、これが、もともと国庫負担金の対象だったものを一般財源化して、どういう事態になっているか。資料三にグラフをつけましたので、見ていただきたいんですね。
就学援助の受給者は、この間の経済危機の中で、このグラフに示されたように、どんどんふえてまいりました。しかし、現在の経済危機にもかかわらず、最近、つまり平成十七、十八、十九というあたりになりますと、伸びが鈍化をしてきております。
ところが、次につけた資料四をごらんいただけますか、これはパネルをつくってまいりましたけれども。今伸びが鈍化したという話をしましたけれども、驚くべきことに、その中で、大阪、山口県、東京、兵庫、この四つの都府県では受給率がこの数年下がっているという結果が出ております。実は、これらの県では就学援助の支給抑制を行っている。自治体による審査基準が厳しくなり、対象者が減らされた結果であります。
文部科学省、こういう現状をつかんでおられますか。
○川端国務大臣 お答えいたします。
委員御指摘の状況に四つがあることは承知をいたしております。それで、御指摘でございますので、私ももう少し詳しく調べてみました。
そういう中で、まず一つは、そのグラフにもありますように、全体という一番下の赤い線から比べると、今御指摘の四都府県はもともと非常に水準が高いんですね。それがどういう背景かは実はまだよく分析できておりませんが、一般の給付率というか、対象割合が非常に高いという四つにそういうことが起こったということであります。
それで、東京都が二・〇三%、十七年から二十年で減ったのでいきますと、東京都内において、この援助対象の基準とか単価を下げたところがないんです。ないのに下がっているということで、ちょっとまだ詳細を把握できていませんが、何か基準を下げたからとかいうことではない。それから、山口県が微減、〇・〇三%ということは、単価を下げたのが岩国市という市が一市下げましたが、あとはそのままでありますので。そして、あとは大阪府は四市で基準を若干下げた。
市町村がこれはどういうふうに実態把握して対応するかということは市町村にゆだねておりますが、数字的にわかったのは今申し上げたまでのことしかわかっておりませんが、毎年そういう調査を行ったところで現実にそういうことが数字として起こったことは事実でありますし、背景は正確にはまだ把握し切れていないのが現状でございます。必ずしも基準や単価を下げたからということではない面もあるのかなというのが、今のところの現状です。
○宮本委員 東京の例を挙げられましたけれども、私、大阪の例を調べてきましたよ。基準の切り下げが明確に行われております。
大阪市では、二〇〇五年で収入目安が四人世帯で三百二十八万円以下とされていたものが、二〇〇九年度には三百九万円以下へと十九万円も認定基準が下がりました。柏原市では、二〇〇五年度三百四十六万四千四百三十三円だったものが、二〇〇九年度には二百九十二万八千四百三十三円にと、何と五十三万六千円、基準が切り下げられております。八尾市では、生活保護基準の一・二倍から一・一倍に切り下げた。泉佐野市では、生活保護基準の一・二倍から一倍へと、ほぼ生活保護基準並みになっております。
岡山県岡山市でも、二〇〇〇年には四百二十万円の認定基準だったものが、二〇〇九年には三百八十七万円と、これも三十三万円も引き下げられております。不認定となった世帯は借金でしのいでいるというふうに聞きました。
経済危機の中で、この就学援助など就学を保障するセーフティーネットが、逆に命綱が切られようとしている、こういう実態については問題だと私は思うんですが、文科大臣の認識をお伺いしたいと思います。
○川端国務大臣 大阪は四市そういう状況があるというのは、私も承知をしております。
一つは、要保護者の認定基準ははっきりしておりまして、国が助成をするということ、二分の一補助するということも決まっているんですが、準要保護者の認定基準は市町村に任されております。そして、先ほど申し上げました学校教育法十九条の規定も含めて、主体は市町村でありますので、基本的には市町村でできるだけ実態に合わせてしっかりやっていただきたいというのが私たちの立場であります。
二十一年の一月に、市区町村の教育委員会に対して、準要保護者の認定基準の変更をしたかどうかということを調査させていただきました。その中では、調査を行った千七百九十五市区町村等のうち、平成二十年度に準要保護児童生徒の認定基準や支給内容の変更を行った自治体が百七十、千七百九十五のうち変更を行ったのは百七十市町村であり、そのうち認定基準の引き下げあるいは支給内容の切り下げを行った市町村が九十市町村、認定基準の引き上げや支給内容の拡充を行ったところが七十四という状況でありまして、まあ、でこぼこはあります。
そういう中で、基準自体は市区町村が主体的に決められるものでありますので、実態に合わせて、できるだけ大変な人が救われるようにという趣旨が生かされるようにということを私たちとしてはこれからもお願いをしていきたいと思いますが、最終的には市町村等が判断をされているというふうに思っております。
〔委員長退席、海江田委員長代理着席〕
○宮本委員 実態調査も、私たち再三にわたって求めてきたわけですけれども、平成十七年と平成二十年、この二回やっただけで、その間の十八、十九というものはつかんでいないわけですね。傾向をつかむだけにとどまっているわけです。
それで、私、こういう切り下げの中身も聞いてきましたけれども、例えば大阪の学校では、昼になると教室から抜けていく生徒がふえている、弁当を持ってこられないから、ひとりバスケットに向かって球を投げて腹が減るのを紛らわせている、こういう報告、本当に貧困に苦しむ実態、子供たちが苦しんでいる実態を聞きました。本当に涙が流れてとまりませんでした。こういうことを本当になくさなければならぬというふうに思います。
憲法二十六条及び教育基本法第四条は、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、」「経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」としております。これは、国及び地方自治体の責任の問題だと思うんですね。
それで、就学援助を一般財源化するときに、こういうことが起こるんじゃないかということが国会で議論になりました。当時の中山文部科学大臣は、市町村における事業が縮小することはない、もしそうじゃないところがあれば指導していきたいと。これは会議録にはっきり答弁が残っております。
実態をつかんで、やはり縮小に向かっているところについては縮小しないように指導すべきではありませんか。
○川端国務大臣 お答えいたします。
当時の中山大臣がそういう御答弁をされております。そういう懸念があったことは事実であります。
総額として、国とそれから市区町村があわせて財政措置をした要保護者、準要保護者に対する総額はふえているんですが、それは実数がふえている現状という部分もあるかもしれませんから、今御指摘のような、基準が下がったところがあることは現実であります。
そういう意味では、私たちとしては、毎年、実績について今後とも把握をする中で、適切にこの趣旨が生かされるように、都道府県等を通じて市区町村に対して就学支援が適切に行われるようには促してまいりたいと思っております。
○宮本委員 やはり地方自治体の財政の大きな困難がこの背景にあるわけなんですね。
それで、どうしてこういうことが起きているか。これは表にもつけましたしパネルも持ってまいりました。これは、私の地元、大阪の泉佐野市の事例、生活と健康を守る会の皆さんが調査した事例ですけれども、実際、地方自治体が支出している就学援助費に対して、国庫負担と交付税交付金は一三%から一八%というような非常に低い水準にしかなっておりません。本来、二分の一国庫負担をしていたはずなんですが、この間、一般財源にした結果、実態は二〇パーから三〇パーしかカバーできていないという状況です。
昨年、文部科学省は、教育安心社会の実現に関する懇談会報告というものを出しました。これは資料六につけております。
この昨年の懇談会報告書では、一般財源化した結果、「市町村の財政力の格差が特に準要保護者に対する就学援助の支給の格差につながっている」という指摘を認めて、この問題を放置すると市町村による就学援助が適切になされないという社会不安につながるおそれがあるとして、国が差額分である六百二十一億円を出せば、各市町村の財政力に左右されず児童生徒の就学機会を保障することができる、去年、既にそういう報告書を出しているんですね。
ですから、これは大いにやるべきだ。六百二十一億円を出すべきだし、もしくは、もとの二分の一の国庫負担に戻すべきだ。これは財政の仕組みの問題ですので財務大臣に、やはりこういうことはきちっとやるべきだと思うんだけれども、財務大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○菅国務大臣 若干ダブりますが、この制度は、もう文科大臣からお話がありましたように、生活保護の受給対象者に就学活動を行う市町村に対して国がその経費の二分の一を補助する一方、要保護者に準じる者への就学援助を行う市町村に対して国が補助をしていたものについては、平成十七年から廃止をいたしたわけであります。
これは、準要保護者の場合は、要保護者よりも困窮度が低く、その認定は各市町村の判断によるものであることから、地域の実情に応じた取り組みにゆだねることが適当という考え方に基づいた改正だと理解しております。
しかしながら、今おっしゃったように、「市町村の財政力の格差が特に準要保護者に対する就学援助の支給の格差につながっている」との指摘もあり、二十二年度については、総務省において、市町村における援助の状況等を踏まえ、地方交付税の配分に当たり、準要保護者への支援が拡充されるよう適切な配慮を行うこととしている、このように承知をいたしております。
○宮本委員 自治体などでは、子ども手当の支給を機に、さらにこの基準を引き下げるんだみたいな議論が出ていると聞きました。先ほど文科大臣からも、子ども手当の趣旨とこの就学援助というものは全然別の制度だという御答弁もありましたから、そのようなことが断固ないように、しっかりと就学援助の制度を守っていきたいというふうに思っております。
官房長官がお見えですので、官房長官にお伺いをしたいと思います。
少人数学級の実施なんです。世界では、二十から三十人学級が標準になっております。日本でも、各自治体では、国民の声に押されて少人数学級の実施が広がってまいりました。三十人学級など少人数学級の実施を認めてこなかったのは、この間、国と東京都だけになっておったんですが、その東京も、部分的少人数学級、小一、中一で三十九人基準というものに踏み出しましたから、もはやこれに踏み出していないのは国だけということになりました。
平野官房長官は、二〇〇一年、民主党・無所属クラブ、日本共産党及び社会民主党・市民連合共同提出の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案の賛成者であり、当時、衆議院文部科学委員会の筆頭理事として、この実現のために御尽力されたと伺っております。
この法案は主に、四十人学級を三十人に引き下げる、こういう内容であったと思いますけれども、官房長官、政権交代した今こそこれに踏み出すべきだと思いますが、官房長官の御見解をお伺いいたします。
○平野国務大臣 宮本委員の方から九年ほど前のお話をちょうだいし、今頭の中で描いているんですが、私どもは、いわゆる先進諸国の中で、教員の持つ生徒数をやはり少なくとも先進国の平均ぐらいまでに下げるべきである、こういう考え方のもとに、少人数学級、その当時の法案ではいわゆる三十人学級を推進する、こういう考え方で法案を出したことも承知いたしておりますし、珍しく共産党さんと一緒にやれた法案だったと思っております。
今、現実におきましても、私どもは、少人数学級、これは川端文科大臣のもとでそういう考え方のもとに検討をいただいている、こういうふうに理解をいたしております。
○宮本委員 既に鈴木文科副大臣がことし、来年度の概算要求に向けて、学級編制基準についての検討を行うということもおっしゃいました。かつてだけでなく今もそういう方向での話であれば、私たち、力を合わせてぜひとも実現するために頑張る思いでありますけれども、文科大臣、ひとつこれについてお答えいただけますか。
○川端国務大臣 お答えする前に、先ほどの部分でちょっと数字の誤りがありましたので。東京都は、二十三区はゼロでしたけれども、東京都の市は二つ条件が下がっているということ。大阪は、四と申し上げましたけれども、六でした。兵庫県は三でした。訂正させていただきます。
学級編制については、昭和五十五年以降、第五次の定数改善計画以降四十人ということで推移して、御案内のとおり、東京都を除く四十六道府県においては独自の少人数学級を実施してこられましたけれども、文部科学省としては、総理指示でも、教育の質と量を充実させるというのが指示でもございます。そういう中で、今回の予算では、四千二百人の定数増ということを何年ぶりかに実質増で手当てすることになりましたけれども、平成二十三年度以降の学級編制のあり方、あるいは教職員定数の改善のあり方について本格的に議論をしようということで、ちょうどきょうの三時に、今やっているところだと思いますが、第一回の関係者のヒアリングを開始いたし、このことに対して着手をいたしました。
今後、教育関係団体、有識者の方々あるいは国民の皆様の御意見を幅広くいただきながら、八月の概算要求までに文部科学省としての一定の結論を取りまとめていきたいというふうに思います。御理解をいただきたいと思います。
○宮本委員 時間ですので終わりますけれども、定員をふやすといっても、行革推進法の五十五条をやはり廃止しなければ本当に正職員として教員をふやすことはできないわけですから、私どもは三十人学級の実施と行革推進法の見直しを改めて求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。