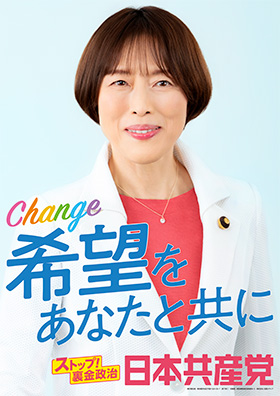159 – 参 – 総務委員会 – 8号 平成16年03月30日
平成十六年三月三十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
愛知 治郎君 吉村剛太郎君
三月二十九日
辞任 補欠選任
舛添 要一君 野沢 太三君
三月三十日
辞任 補欠選任
野沢 太三君 野上浩太郎君
山内 俊夫君 愛知 治郎君
高嶋 良充君 堀 利和君
谷林 正昭君 榛葉賀津也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 景山俊太郎君
理 事
柏村 武昭君
岸 宏一君
山崎 力君
内藤 正光君
広中和歌子君
委 員
愛知 治郎君
狩野 安君
片山虎之助君
久世 公堯君
椎名 一保君
世耕 弘成君
野上浩太郎君
吉村剛太郎君
小川 敏夫君
榛葉賀津也君
高橋 千秋君
谷林 正昭君
堀 利和君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
鶴岡 洋君
日笠 勝之君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 麻生 太郎君
副大臣
総務副大臣 田端 正広君
総務副大臣 山口 俊一君
大臣政務官
総務大臣政務官 松本 純君
文部科学大臣政
務官 馳 浩君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局取引部長 松山 隆英君
総務省情報通信
政策局長 武智 健二君
参考人
日本放送協会会
長 海老沢勝二君
日本放送協会専
務理事・技師長 吉野 武彦君
日本放送協会専
務理事 関根 昭義君
日本放送協会理
事 安岡 裕幸君
日本放送協会理
事 宮下 宣裕君
日本放送協会理
事 和崎 信哉君
日本放送協会理
事 野島 直樹君
日本放送協会理
事 中山 壮介君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認
を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
<教育テレビへの字幕付与にも努力を>
宮本岳志君 日本共産党の宮本岳志です。
まず、お伺いしますけれども、教育テレビについて、いわゆる字幕付与可能な番組に対する字幕付与率の目標を二〇〇四年度から二〇〇七年度まで年ごとにお答えいただけますか。
参考人(関根昭義君) 教育テレビにつきましては、私ども、放送総時間に占める割合の字幕化を進めているところであります。したがいまして、いわゆる行政指針に基づいた、行政の指針に基づいた数値は出していませんけれども、御指摘の件につきまして換算しましたところ、この平成十六年度は大体二七%程度であります。
宮本岳志君 平成十六年度から十九年度まで出してください。
参考人(関根昭義君) ごめんなさい。十七年が二八%程度です。十八年が二九%程度、そして平成十九年が三一%程度です。
宮本岳志君 NHKは、総合テレビについては一年前倒しして二〇〇六年度に字幕付与可能な番組の一〇〇%に字幕を付けると積極的な姿勢をお示しをいただいているわけですね。ところが、教育テレビについては大変低いんですよ。それを今日お付けしたグラフにいたしました。同じものをここにパネルにしてございます。(資料提示)この青丸が総合テレビ、これはもう二〇〇六年に一〇〇%という勢いで進んでおります。赤丸が教育テレビ、どんと低いわけですね。二〇〇七年になっても付与可能な番組のわずか三一%にしか字幕を付けないと。こういう目標であることは非常に重大だと思うんです。総合では民放キー局をはるかに上回る姿勢で取り組んでいるNHKが教育テレビではこういう状況にあると。
これはNHKの会長に少しお伺いしたいんですが、教育テレビの字幕化の目標がこう低い数値であるというのは、教育テレビの障害者向け情報保障の必要性は低いとまさかお考えじゃないと思うんですが、いかがでしょうか、会長。
参考人(関根昭義君) 私ども、限られた資源、経営資源の中でそれをどうやって有効に使っていくのかということを考えていまして、これは視聴者のいろんな御要望もありまして、まず何よりも基幹放送である総合テレビ、ここの字幕拡充というのを最優先課題として取り上げているということです。
宮本岳志君 教育テレビは「子どもに親しまれ、暮らしに役立つ波」と、このNHKビジョンの中でもNHK自身がおっしゃっております。ニーズも高いんですね。そして、聴覚に障害のある子供たちにとっては文字を学び情報を得る重要な手段なんです。しかも、教育テレビは生放送が少ないですから、ほとんどが字幕付与可能なわけですね。ところが、実は九七年の国の指針で、ガイドラインで、総合テレビはすべてに字幕付与となっているにもかかわらず、教育テレビの方はできる限り多く付与と、こうなっているんですね。だから、教育テレビの取組というのは後れているわけです。
そこで、これは総務大臣に聞くんですけれども、この字幕の指針について、ガイドラインについて、国のですよ、教育テレビについても総合テレビと同じようにすべてに字幕付与というふうに改める必要があると私は思うんですが、総務大臣、いかがでしょう。
国務大臣(麻生太郎君) 基本的には、これはNHKという独立した法人、法人の経営が、自分の抱えております限られた資金、資本をどういう優先順位で投下していくかという話なんだと思っておりますので、総合がまず一〇〇%を目指すという方向になって、その方向で動いておるということは間違いない、努力はまず認めにゃいかぬところだと思うんですね。その割に総合は後れておるではないかと……
宮本岳志君 教育ね。
国務大臣(麻生太郎君) 教育は後れておるではないかという事実はそうかと思いますが、そちらのところをまず最初にやらにゃいかぬということを決めたわけですから、その方向でやっておるということはそれなりに認めた上じゃないと、おまえ、こっちやっておれ、こっちはなっとらぬじゃないかと言ったって、それは言われた方も困るんじゃないでしょうか。
宮本岳志君 それはもう重々認めているんですよ。それで、民放だって後れていたんですよね。それが年次目標を持ってやるようになってぐんと、これ民放なんですよ。民放だって二〇〇七年に向けてすごく頑張らにゃならぬと、こうなっているわけですね。だから、それぞれ一〇〇%目指して頑張っているわけですけれども、教育だけは一〇〇%を目指してない、これはいかがなものかと。やっぱり一〇〇%を目指して、総合もそうだし、民放も頑張ってもらっているんだからということを私申し上げたんですね。
それで、そもそも、しかしこの問題について言わしていただけば、実はこの先ほどのグラフというのは、これは番組、付与可能と言われる放送番組に対する字幕付与率の話なんです。だから、生番組とかニュースとかそういうものは除いた番組の一〇〇%を付けようという議論なんですね。
ところが、こういう国は日本だけなんですよ。こちら側に、皆さん方には二枚目のグラフを付けたんですが、アメリカ、イギリスとの比較というのをお付けをいたしました。(資料提示)
これは、アメリカの四大ネットワークとイギリスBBCの目標をグラフにしているんですが、これは総放送時間、もう全部の放送時間に対する目標と計画なんですね。見ていただいたら分かるように、アメリカは二〇〇六年に総放送、すべての、一〇〇%をやろうということで頑張っていると。BBCも二〇〇八年過ぎには一〇〇%と。ところが、NHK総合でも総放送時間ということで考えればわずか四五%にとどまっておりますし、教育はほとんど番組、字幕付与可能ですから、生が少ないですから同じように、同じようなラインになるわけですけれども、こういうことは歴然とすると思うんですね。
私どもの繰り返しの要求に、字幕付与不可能だと割り振られていたニュース、不可能と言われていたニュースにNHKが字幕をお付けになって四年がたちました。それで、NHKは今ニュースだけでなく、紅白歌合戦にも、それからスポーツ番組にも字幕をお付けになっております。民放でも日本テレビとかあるいは東京放送とかフジテレビでは字幕付きのニュースも、全部じゃないですが字幕付きのものも民放でも始まっているんです。だから、今や生は無理とかスポーツは無理とか、字幕付与可能とか不可能とかに余り意味は、だんだん垣根がなくなってきているわけですよ。
そこで、なるほど二〇〇七年に向けてこの目標の達成のために、このこっちの方の、頑張ると、これはもう当然のことなんですけれども、二〇〇七年のその先を展望したときに、やっぱり日本も徐々に世界基準といいますか、総放送時間の一〇〇%を目標にする、それを目指して計画を持っていくということが、そういう検討がこれから求められるんじゃないかと私思うんですけれども、この点についての総務大臣の御見解をお伺いしたいと思うんです。
国務大臣(麻生太郎君) 漢字って、ワープロやったことあるから知っているでしょうけれども、ワープロ、分かりますね。あれ、漢字転換が一回やるんですよね、あれ。アルファベットの場合、ざっとそのまま打てばいいから私でも結構早く打てる方ですけれども、漢字転換一発入れて、それが合っているかどうか再確認した上で確認するという手間というのは、あれ結構大変なんですよ。そのタイミングのずれというのは結構でかいという技術的な話は、これ技術的な問題として知っておいていただかぬと、これは言われた方もなかなか難しい、というのは技術的な話として。その技術が更に進んで、音声転換ができますとかいうような技術まで今上がってきますとまた少し変わったものになってくるんだとは思いますけれども、今の段階でと言われると、これはほかの国ほど、いわゆる横文字のアルファベットをそのまま打てばそのままいいというのとは少し違うんじゃないかなという感じが、その種のことを結構分かっている方から言わせると、技術的には結構大変かなという感じはしますが、いずれにしても、一〇〇%達成した後という話は、ひとつ改めて検討する値打ちがあると思います。
宮本岳志君 まあその日本語で一部できているわけですから、検討には値すると、そういう御答弁いただいたと思っております。
<「下請けいじめ」の防止に努力と答弁>
宮本岳志君 次に、テレビ番組制作の委託取引問題についてお伺いしたいと思うんです。
先ほど八田委員が取り上げた番組改変訴訟の東京地裁判決をめぐっても、新聞では放送局、下請、孫請というこの業界で日常的に行われているシステムの在り方に問題を投げ掛けたとの指摘がされております。
この問題で、昨年、公正取引委員会はテレビ番組制作業における下請取引実態という調査を行って、その報告書もこの間、こうして出されております。(資料提示)今日は公正取引委員会に来ていただいておりますけれども、放送業界では従来から優越的地位の濫用が問題となってまいりましたが、改正下請法の施行を控え、公正取引委員会では放送業界で特にどのような点が問題になるとお考えか、お聞かせいただけますか。
政府参考人(松山隆英君) お答えいたします。
今御指摘の公正取引委員会の調査結果によりますと、放送局の制作会社に対して放送番組を制作委託取引を行う際に、優越的地位の濫用が生じてくるケースといたしまして幾つかございますが、一般的に見られますのは、まず委託内容なり取引条件を明確に記載した発注書面、これが交付されてないケースが見受けられる、あるいは、著作権を委託者に譲渡するというのがございますが、その場合の譲渡対価が代金に反映されていないという問題、それから委託者の指示に基づきまして作成した番組につきまして不当なやり直しが求められるといったような問題があると考えております。
公正取引委員会では、このような問題に対処するために、下請法あるいは独占禁止法の厳正、的確な運用に努めてまいりたいと考えております。
宮本岳志君 何点か述べられましたが、番組内容の変更というようなことについても、きちっと、下請、孫請との関係ということが今問題となってくるという話があったと思うんですね。先ほどの判決でも、番組の編集権は認められたと胸を張るわけですけれども、末端の正に取材をした会社の責任が問われるという事態になっているわけですよね。
それで、NHKは昨年三月に自主基準を定め、公表いたしました。四月の改正下請法の施行前に自ら決めたこの自主基準を守ることはもちろん、是非、番組取引の近代化に範を示すべきだとNHKが、私はそう思いますけれども、これはNHKの会長、範を示す御決意をお示しいただきたいと思います。
参考人(関根昭義君) 御指摘のように、私どもは去年の三月、自主基準というのを決めています。もとより、外部プロダクションとの間等でいろんな取引が発生しますけれども、いやしくも、取引上の常識に反して無理を言ったり、また、仕事上の迷惑、不利益、そういったものを押し付けたりすることがないように、重々注意しながらやっていることであります。
我々としては、これまでも適正な取引をやってきていますけれども、こういう改正下請法が施行されるということもありまして、これからはいやしくも下請いじめ、そういったことが言われたりしないように、これから取引には万全を期していきたいというふうに考えています。
<有事の「指定公共機関」は拒否すべき>
宮本岳志君 最後に、有事法制と指定公共機関の指定について聞きたいと思います。
これはもちろん我が党は反対いたしましたが、昨年の通常国会で成立した武力攻撃事態法では、放送局を指定公共機関とする制度が設けられました。これに対して、既に民放連は、国民の知る権利に奉仕する報道機関が政府に奉仕するものに変質しかねないとして、報道の自由に対する懸念が払拭されない限り、この制度は受け入れられないとの態度を表明しております。しかしNHKは、先日、メディア研究者二十七氏の質問状に対して、NHKが有事の際に指定公共機関に指定されることについて賛否を明らかにしないというあいまいな態度をお取りになりました。
会長、なぜ民放連のように受け入れられないとはっきり言えないんですか。
参考人(海老沢勝二君) 私どもは、放送を通じて国民の生命、財産を守るというのが我々の使命であります。したがって、災害に対する基本法でも公共指定機関に指定されて、そういう緊急の情報、警報あるいは緊急避難等については的確に視聴者の信頼にこたえられるようにこれまでも放送しておりますし、今後もやっていくわけでありますが、今度の有事立法に対しても、あくまでも我々は視聴者・国民の立場に立って生命、財産を守るというのが我々の使命でありますから、指定公共機関になろうがなるまいが、なったにしても私は反対する気はありませんし、またそれはこれから国会で審議されるものでありますから、私がここで先走って言うあれはありませんので、我々はどういう時代になっても、あくまでも言論の自由、思想の自由を守りながら国民の生命、財産を守るようにやっていくのが我々の使命だろうと思っています。
宮本岳志君 もちろん民放だって、指定公共機関に指定を受け入れられないと言っているからといって、視聴者の生命や財産にかかわる緊急情報の放送をやらないと言っているわけじゃないんですよ。そんな指定されなくてもやるんだと、みんな、だからそんな指定は必要ないと、そういうふうにおっしゃっているわけですよね。
それで、NHKがやはり、私はNHKがこの法案への賛否を言えとか、あるいは指定公共機関制度への賛否を言えと言っているんじゃないんですよ。それはいろんな立場があるでしょう。しかし、少なくとも放送局を指定公共機関に指定するというのはふさわしくないということを民放も言っているわけですから、なぜその態度がはっきり打ち出せないのかということを指摘をしているわけですよ。
先ほど受信料の収納問題というのも出されました。会長からは視聴者との信頼ということも言われたわけでありますけれども、正にNHKが国営放送ではなく公共放送として受信料によって成り立っていると、独立していると、だからこそ国民は信頼しているわけですから、やはりこの点、報道の自由をきちっと守るという態度を貫いていただくことを強く求めて、私の質問を終わりたいと思います。